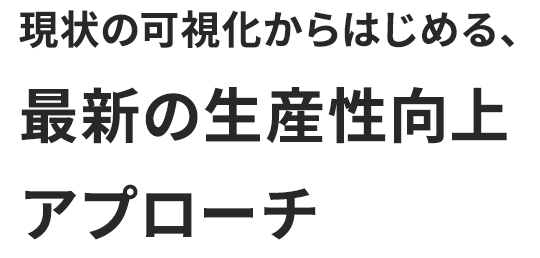

人手不足や原料の高騰に対抗するため、DXの一環として、生成AIエージェントやRPAをはじめ、
さまざまなITツールの導入を急ぐ企業が増えています。
しかし、本当の意味で効果的な改善を行うには、導入の目的、
すなわち「課題の正確な把握」こそが、改善の成否を左右します。
今回は、課題の把握のための最新のアプローチをご紹介します。
池田 睦(いけだ むつみ)
NECネクサソリューションズ株式会社
コンサルティング統括部
ガバナンス・テクノロジーグループ マネージャ
2009年よりコンサルティング業務に従事。
AI導入アドバイスのほか、データ活用(BI/AI)を駆使した業務プロセス改善による効率化を担当。
ITコーディネータ/情報処理安全確保支援士/DX検定 プロフェッショナルレベル

 生産性向上の第一歩は、現場の課題を正しく理解すること
生産性向上の第一歩は、現場の課題を正しく理解すること
近年、経営環境はますます厳しさを増し、限られたリソースで生産性を高めることが求められています。
一方で、ITの進化や生成AIなどの新技術の登場により、業務効率化のための手段は、ますます便利になっています。
このような環境下では、「もっと生産性の上がるITツールを!」と期待し、様々なツールを導入したくなるものですが、いざ導入すると、思うような効果が出なかったり、結局使われなくなってしまうケースもよく見受けられます。
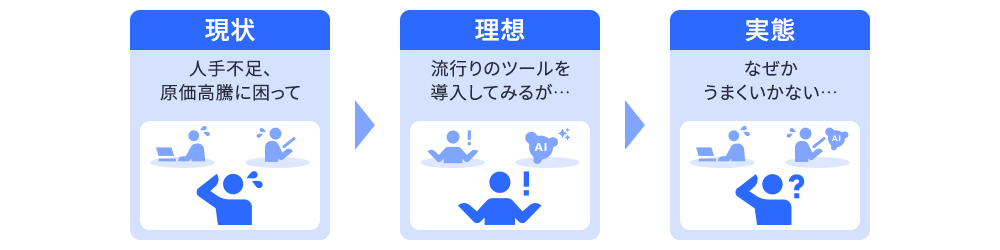
ツール導入の理想と実態
なぜ、こうした問題が起きるのでしょうか。
その大きな原因は、現場の課題を正確に把握できていないことにあります。
多くは「自社の課題くらい分かっている」と考えがちですが、「その課題がどれだけの損失を生んでいるのか」「解決した場合、どのくらい効果があるのか」を具体的な数値で示すのは難しいものです。
課題を定量的に捉えられれば、ツール導入の費用対効果をきちんと検討し、本当に役立つITを選ぶことができるでしょう。
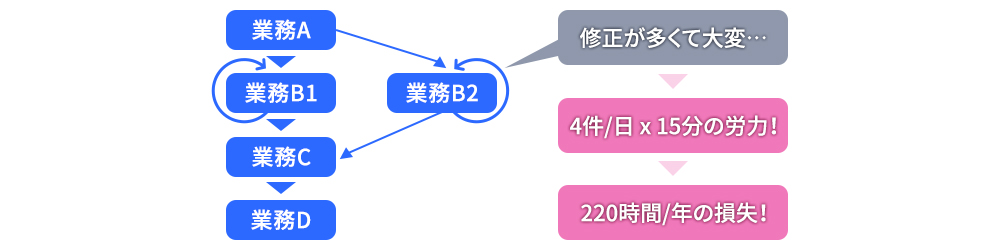
課題の定量的な把握
 定量的な課題把握の困難さ
定量的な課題把握の困難さ
しかし、定量的な課題把握というのは、意外に難しいものです。
現場ヒアリングは、受ける側から見て時間も手間もかかる上に、主観が入り混じり、抜け漏れも発生しやすくなり、正確な把握ができません。
例えば、コンサルファームなどでは一日中後ろから業務を観察し、その詳細をメモするということまで行うほど、重要な作業であるにもかかわらず、時間と労力がかかります。
その他、定量的な課題把握における課題を下記に並べました。
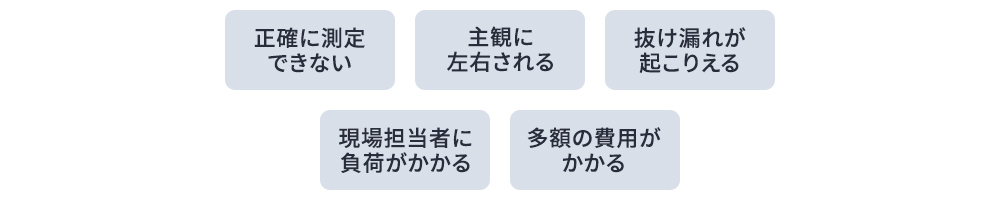
効果的な生産性向上のために、現状を定量的に把握したいのに、それは困難である。
このようなジレンマを解消するための手段、「プロセスマイニング(Process Mining)」をご紹介します。
 プロセスマイニングによる現状可視化
プロセスマイニングによる現状可視化
プロセスマイニングとは、「ログデータ」をもとに業務プロセスを再現し、分析する手法です。
例えば皆さんが日々利用している、基幹システムや、業務アプリケーションには、「皆さんがどのように業務を行ったか」を知る手がかりが、ふんだんに含まれています。
これらを用いて可視化を行うことで、「誰が」「なんの作業に」「どの程度の時間をかけて」作業しているのか、その仕事は「何件」行われているのかを、一目で把握することができます。
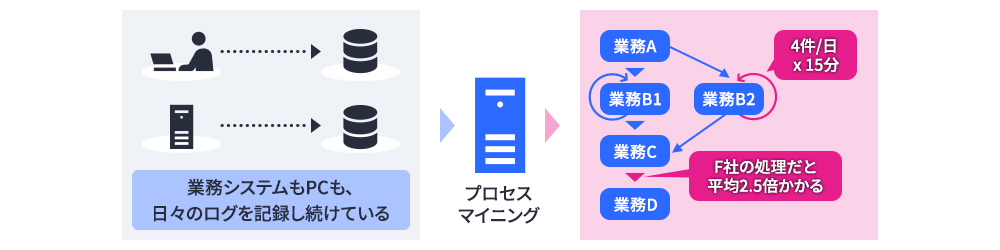
プロセスマイニングによる可視化イメージ
このアプローチであれば、ログという事実をベースに解析するため、従来のヒアリングをベースとした現状把握に比べ、定量的な現状把握がしやすくなります。
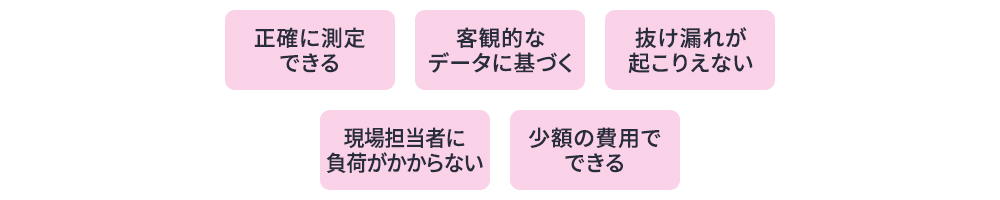
 まとめ
まとめ
全てのDX・業務改善は、現状の正確な把握が最初の重要なポイントになります。
ただし、「正確な把握」には、通常、多大な労力や問題がつきまといます。
NECネクサソリューションズでは、「業務プロセス可視化サービス」を通して、プロセスマイニングによる現状の正確な把握をご支援しています。
改善の第一歩を確実に踏み出すために、プロセスマイニングによる業務の可視化を始めてみませんか?
2025年9月