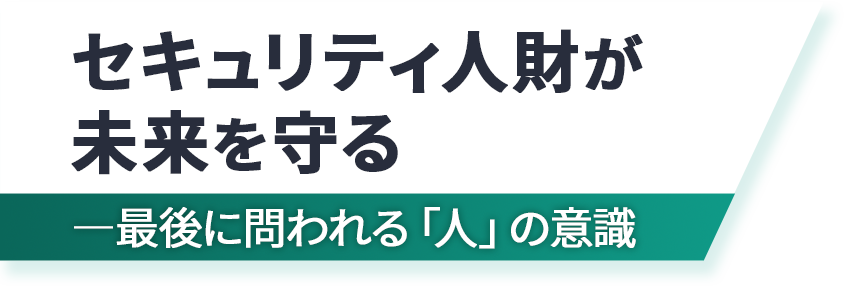

笠井 靖記(かさい やすのり)
NECネクサソリューションズ
SI戦略推進統括部/SI戦略グループ マネージャ
2010年代よりセキュリティ部門に所属し、WAFの開発や脆弱性診断サービスの提供に従事。その後は、最新のセキュリティ動向や脆弱性情報の収集、サイバー演習やeラーニングの実施、社内外でのインシデント対応を通じて、全社のセキュリティ対応力の向上に取り組んでいます。
CISSP(Certified Information Systems Security Professional)、CEH(Certified Ethical Hacker)、CND(Certified Network Defender)
IPA情報処理安全確保支援士 実践講習認定講師、Certified EC-Council Instructor

 ランサムウェアが突きつける現実
ランサムウェアが突きつける現実
サイバー空間における脅威は年々多様化し、その影響は社会全体に広がっています。特にランサムウェアによる被害は深刻で、国内外を問わず、多くの企業や自治体、教育機関が標的となってきました。情報資産の暗号化や業務の停止、さらには金銭的損失に至るまで、その影響範囲は計り知れません。例えば、近年報告された事例として、ある自治体の委託先がランサムウェアに感染し、膨大な個人情報が流出する深刻な事態となりました。こうした被害はもはや一部の組織だけの問題ではなく、あらゆる組織が直面しうる現実となっています。
 被害の多くは「既知の脆弱性」から
被害の多くは「既知の脆弱性」から
多くの場合、その原因は「既知の脆弱性」にあります。セキュリティベンダーや各種機関からは日々、脆弱性情報や修正パッチが提供されています。それにもかかわらず、企業や組織の中にはパッチ適用が遅れる、あるいは未適用のまま運用されるシステムが存在します。こうした状態は、攻撃者にとって格好の侵入口となります。
IPAの「情報セキュリティ白書2024」によれば、ランサムウェア等で被害を受けた機器・システムのうち40%が最新のセキュリティパッチを適用していたのに対し、60%は少なくとも一つ以上の未適用パッチが残されていたという調査結果があります[1]。さらに、2023年度の「中小企業等実態調査」では、サイバーインシデントを経験した企業(n=975)のうち、「不正アクセス被害」があった企業(n=419)の約48.0%が、「脆弱性(セキュリティパッチの未適用等)を突かれた」と回答しています[2]。これは、パッチ未適用が単なる技術的な不備ではなく、実際の被害の入り口として非常に頻繁に利用されていることを示しています。従来から言われる基本対策の徹底が、いかに重要かを物語る数字です。
 軽視されがちな「基本的な防御策」
軽視されがちな「基本的な防御策」
もう一つの典型例が「安易なパスワード設定」です。いまだに推測容易な文字列や、複数システムでの使い回しが後を絶ちません。攻撃者が用いる辞書攻撃や総当たり攻撃は高度な技術を必要とせず、それでも被害が繰り返されるのは、基本的なルールを守らない利用者が存在するからです。
特に中小規模の企業では、IT管理担当者が不在のために、パスワードポリシーの設定や監視が行き届かず、結果として簡単に侵入されてしまうことがあります。
また、従来から指摘されている問題の一つに「システムを安易な初期設定のまま運用する」ケースがあります。不要なサービスを有効化したまま運用したり、既定アカウントのままシステムを公開したりすることで、攻撃者に余計な足掛かりを与えてしまいます。こうした基本対策の軽視が、被害の発生率を高めています。
基本的な対策を徹底していれば防げた事例は多く存在します。しかし現実には、パッチの適用、強固なパスワード、不要な機能の無効化といった基本を守らないケースが目立ちます。
その原因の一つは「知識として理解していても、行動に結びつかない」点にあります。多忙な業務やIT部門の人員不足、また心理的な抵抗感によって後回しにされることもあります。さらに経営層がセキュリティを単なるコストと見なし、優先度を低くしてしまう文化も問題です。
 最終的に問われる「人の意識」
最終的に問われる「人の意識」
セキュリティの最終防衛線は「人」です。システムの堅牢さや最新技術も重要ですが、判断や操作を行うのは人間です。パッチを適用するのも、パスワードを設定するのも、不要なサービスを止めるかどうか決めるのも人です。どれほど高度な防御を用意しても、人の意識が低ければ守りは脆弱になります。逆に、意識が高く習慣化されていれば、多くの攻撃を未然に防ぐことができます。
ここで重要になるのが「セキュリティアウェアネス」です。単なる知識として覚えるだけでなく、日常業務の中で自然と正しい判断ができる状態を作ることが求められます。具体的には、定期的なセキュリティ教育、模擬攻撃演習、インシデント発生時のロールプレイ、経営層からの継続的なメッセージ発信、相談しやすい社内環境整備、監視とフィードバックなど、複合的な施策が有効です。これらにより、従業員一人ひとりの意識を行動に結びつけ、組織全体の防御力を高めることができます。
 人財こそ最大の資産
人財こそ最大の資産
サイバーセキュリティを支える最大の資産は「人財」です。技術や製品だけではなく、組織の一人ひとりが意識を高く持ち、日常の判断や行動に反映させることが、ランサムウェアや様々な脅威から未来を守る決定的な要素となります。意識を高める文化と習慣の醸成こそ、セキュリティの核心です。
2025年11月
 IPA, 情報セキュリティ白書2024, 2024
IPA, 情報セキュリティ白書2024, 2024 IPA, 2024年度中小企業等実態調査 速報版, 2024
IPA, 2024年度中小企業等実態調査 速報版, 2024