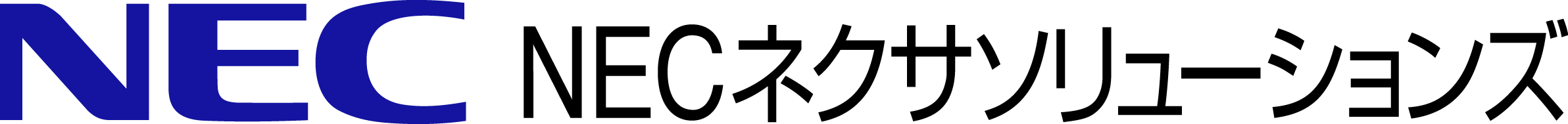ERPとは?必要性や種類、導入のメリットをわかりやすく解説

業務の効率化を図る方法として、ERPの導入をおすすめします。ERPとは、企業の経営資源を一元管理できる便利なシステムです。本記事では、ERPの特徴を導入フローや選び方と併せて徹底解説しています。ぜひ最後までご覧ください。
ERPとは
ERPとは、企業の4大経営資源といわれる、ヒト(人的資源)モノ(物的資源)カネ(経営資金)情報(無形資源)の管理を一まとめにし、計画的かつ最適な配分を行うことで効率的な業務遂行を可能にする仕組みのことを指します。正式名称である「Enterprise Resource Planning」を略してERPと呼ばれており、日本語では「企業資源計画」という意味です。
ERPは、生産管理手法である資材所要量計画「MRP(Material Requirements Planning)」が語源になっています。つまり、製造業における無駄なく資材の購入を行うための計画をビジネス分野にアレンジして生み出された手法がERPなのです。
ERPの必要性
ERPが必要とされる理由は、企業における全体の業務を効率的に管理できるようになるためです。
従来のシステムでは、それぞれの部門ごとに情報管理を行う仕組みであり、各管理部門の間で連携が取れていませんでした。業務を行うごとに人為的な作業が介在するため、手間がかかるうえ入力ミスや内容の重複などの失敗が多発していたのです。情報の保存場所もそれぞれ異なっており、分析を行う目的で抽出しようにも見つけ出すまで時間を要する点も問題視されていました。
ERPを導入すると、部門ごとの壁が取り払われ情報を一元管理できるようになります。入力は最低限で済むため、人為的なミスを大幅に減らせるでしょう。また、入力した内容は常に最新の状態であるため、部門ごとでの管理と比べ、合理的かつ素早い情報共有が可能です。
ERPと基幹システムの違い
企業経営においてメインとなるさまざまな業務を支援する仕組みの総称を「基幹システム」といいます。
基幹システムは主に次の6種類です。
- 販売管理システム
- 購買管理システム
- 在庫管理システム
- 生産管理システム
- 財務会計システム
- 給与計算システム
企業の業態や部署によって、どれが基幹システムとなるかが異なります。基幹システムは特定の機能に特化しており、それぞれが独立しているのが特徴です。他の管理部門と情報を共有するには、システムを連携させなくてはなりません。カバーする業務の範囲が限定されているため、比較的安価かつ短時間で導入できる場合が多いといえます。
一方、ERPでは各業務を効率的に行えるよう全ての部門の管理が一元化されているのが特徴です。情報の共有・連携が即時に行われるため経営の状態確認がしやすく、方針や戦略の決定をスムーズに行えるでしょう。業務全体を巻き込んだシステムのため、導入にかかるコストや時間が多く、社内の規定や業務フローの見直しが必要になる場合があります。
ERPの主な機能
ここではERPの主な機能について解説します。
| 機能 | 具体的な業務 |
|---|---|
| 販売管理 | 見積、受注、売上、請求、入金、売掛金管理 |
| 購買在庫 | 発注、検収、仕入、在庫、支払、買掛金管理 |
| 財務会計 | 財務諸表・元帳作成、経費精算、固定資産管理、決算処理 |
| 給与計算 | 勤怠管理、給与計算、社会保険計算、年末調整、給与・賞与明細発行 |
販売管理
販売管理は、商品・サービスの流通に関する業務を一貫して把握できる機能です。顧客からの注文への対応はもちろん、期間・店舗ごとの状況確認や報告書の作成を行う機能が実装されているERPもあります。
購買在庫
購買在庫は、商品の仕入や製品の原材料および製造に必要な備品などの発注を取り仕切る機能です。商品調達に関する業務を一つにまとめ効率よく管理できるため、生産性の向上につながります。
財務会計
財務会計は、資金繰表や消費税申告書、損益計算書などの財務諸表の作成、管理を行う機能です。財務会計は、企業の経営状況や財政状況を金融機関、株主、税務署、投資家などのステークホルダーに開示することを目的として行われます。
給与計算
給与計算は、従業員の勤怠を管理して給与を計算する機能です。ほかにも、給与明細の作成やWeb上で給与明細を確認できる機能が付いている場合もあります。保険に関する算定基礎届や月額変更届の作成機能もあり、従業員数が多い企業では管理が煩雑になりやすい業務の効率化が可能です。
ERPの種類
ERPは主に、業態や業務内容に合わせて選べる3つの種類があります。
- 統合型ERP
- コンポーネント型ERP
- 業務ソフト型ERP
| コスト | 開発期間 | 特徴 | |
|---|---|---|---|
| 統合型ERP | 高 | 長い | 全ての部門を総合的に管理できる |
| コンポーネント型ERP | 低 | 短い | 必要な機能や部品を組み合わせられる |
| 業務ソフト型ERP | 低 | 短い | 特定の業務のみに特化している |
統合型ERPは全業務をカバーできるタイプの製品です。適用範囲が広いため開発期間が長期に渡り、それに伴い費用も高額になるケースが多いといえます。
コンポーネント型は、別個に販売されているERPの機能や部品を組み合わせられるタイプの製品です。機能や部品ごとに料金が設定されているため、組み合わせによってコストや開発期間が異なります。
業務ソフト型ERPは、各機能の特定の業務のみを管理する製品です。機能が限定されており、他の種類と比べてコストや開発期間を抑えられます。
統合型ERP
統合型ERPは、経営に関わる全ての業務を包括的に管理できる機能を有しています。一般的に、ERPといえば統合型をイメージする方が多いでしょう。市場にはITベンダーが提供するERP製品が豊富にあります。
統合型ERPを導入すると、部門間の連携が取れ、状況を統括して素早い経営判断とそれに合わせた的確な指示が可能です。また、セキュリティへの配慮も万全であり、機密事項や顧客データなどを保護できるでしょう。
しかしその分、費用が高く開発期間が長期化するという点に注意して導入する必要があります。
コンポーネント型ERP
コンポーネント型ERPはそれぞれの機能や部品を組み合わせられるタイプの製品です。一つの部門に関わる幅広い業務の管理ができ、自社の特徴に合わせて導入しやすいという特徴があります。
販売・営業など必要に応じてチョイスできるため、すでに構築してあるシステムに機能や部品を追加したい場合に便利でしょう。単一の機能や部品だけを選ぶこともでき、部門ごとに異なるERPを導入するケースにも対応可能です。
選ぶ機能や部品数や組み合わせによって導入にかかる費用や開発期間が異なります。必要に応じて機能を組み合わせれば、短期間に最低限のコストで導入できるでしょう。
業務ソフト型ERP
業務ソフト型ERPとは、ある部門の単一業務を管理するタイプの製品です。会計ソフトや受注を管理するシステムなどといえばイメージしやすいかもしれません。
一つの業務を管理する機能に特化しているため、担当者の負担軽減や業務の効率化につながります。他のタイプと比べ、リーズナブルなうえ開発期間も短時間で済み、必要なときにすぐ導入できるという点で優れているシステムです。
一方で、部門・業務間でデータが一元管理されないため、整合性を確保するには業務の煩雑さを招く可能性があります。
ERPの導入方法は2種類
ERPには、「クラウド型」と「オンプレミス型」の2タイプの導入方法があります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| クラウド型 |
|
|
| オンプレミス型 |
|
|
クラウド型は低コストで手軽に導入でき、オンラインに関わるさまざまなメリット・デメリットがあるのが特徴です。一方、オンプレミス型は独自性のあるERPを構築し自社で運用するシステムであるかわりに手間やコストがかかるのが難点だといえます。
クラウド型
クラウド型とは、インターネット上にプラットフォームを持ち、全ての業務管理をオンラインで行えるERPです。独自に構築されたシステムではなく、定額制で提供されることも多いサービスです。
クラウド型のメリット
クラウド型には、次のようなメリットがあります。
- 低コストで導入できる
- どこからでもアクセスできる
- 管理にかかる負担が減らせる
- 復旧が容易にできる
クラウド型ERPはシステム自体を買い上げるタイプではなく定額制での販売形態もあるため、初期費用を抑えられます。システム導入のためのハードや特定のソフトを購入する必要もありません。インターネットにつなげる環境さえあれば導入できるうえ、社外からでもアクセスできます。
また、管理は提供元が行うため、導入することで新たな負担が生じない点や災害時にシステムダウンした際の復旧が早い点もメリットです。
クラウド型のデメリット
一方、クラウド型には以下のデメリットも存在します。
- 独自のカスタマイズが不可能
- オフラインでは利用できない
- 自社の管理の手が届かない部分がある
クラウド型のERPでは完成されているERPシステムを導入するため、デフォルトの機能以外は使用できません。機能を追加できるERP製品もありますが、あくまで提供されるサービスを受け取るのみであり、独自のカスタマイズは不可能です。
また、インターネットにつなげない環境ではアクセスできないというデメリットも存在します。提供元に管理してもらえるのは便利である反面、自社で監視できないということでもありますので導入前にサービス内容を確実に把握しておきましょう。
オンプレミス型
オンプレミス型は、注文内容に合わせて構築したい機能を買い取り、自社で設置・運用するタイプのERPです。
オンプレミス型のメリット
オンプレミス型のERPには、以下のメリットがあります。
- 独自の要望を機能に反映できる
- 既存の自社システムに追加できる
- セキュリティに関するリスクが低い
オンプレミス型では、細かい要望を製品の機能に反映させられます。他社とは異なるシステムを構築できるうえ、購入後のカスタマイズも可能です。
自社内に設置するERPですので、クラウド型とは異なり常に情報漏えいのリスクにさらされているわけではないという点もメリットです。
オンプレミス型のデメリット
しかし、オンプレミス型には次のデメリットも存在します。
- 導入にかかる費用が高額になる
- 運用に専門知識を持つ担当者が求められる
- 災害やトラブルに弱い
オンプレミス型のERPは自由度が高い反面、導入のための初期費用がかかり、求める機能が多いほど高額になりやすいです。また、すでに構築されたシステムではなく管理・運用も自社で行う必要があるため、専門知識を持つ担当者が必要であり、新たに人件費がかかる場合もあります。
さらに、災害やトラブルが生じた際の復旧が容易ではなく、担当者の業務負荷が高くなる場合も少なくありません。
ERPを導入するメリット
ERPを導入することで、次のようなメリットを得られます。
- データの一元化ができる
- 情報が可視化される
- 管理情報を常に最新の状態に保てる
ERPを社内業務に導入した場合、あらゆる情報が一元化され部署間や支店間と連携が可能です。一つの作業が全体に反映されるため、業務の標準化が図れ、入力ミスや業務のムダが減るなど効率的に業務を遂行できるでしょう。
また、さまざまな情報が可視化されるため、情報の確認やデータの比較が容易にできます。企業内ルールが統一でき、違反のチェックがしやすくなるため、コンプライアンスの徹底にも繋げることが可能です。
さらに、ERPでは各部門の最新の情報が常に確認でき、売上や在庫などのさまざまなデータが時系列に沿って反映されます。このため正確かつ迅速な情報収集ができるようになり、事業戦略など意思決定の判断を素早く行えるようになる点もメリットだといえるでしょう。
ERPを導入するデメリット
一方で、ERPには以下のようなデメリットがある点を理解しておきましょう。
- 導入・運用にコストがかかる
- セキュリティ対策およびシステムの更新を行う必要がある
- サービスの選定が難しい
- 社員教育を徹底する必要がある
ERPは導入にコストがかかるという点がデメリットです。特にオンプレミス型のERPでは数百万から数千万単位のコストがかかる場合があり、運用のために新たな人件費がかかるケースも考慮しなくてはなりません。セキュリティ対策やシステムの更新を定期的に行わなくてはならず、そのたびにも費用がかかります。初期費用や運用にかかるコストを抑えるためには、クラウド型の利用を検討するのがおすすめです。
また、さまざまな企業が数多くのERPパッケージを提供しているため、選定に時間がかかる可能性もあります。目的や要望を明確にして比較検討のうえ、自社に適したERPを選びましょう。
ERPは一つの操作が全体に反映されます。そのため、人為的なミスが生じた場合の影響が大きく、新システムの導入に抵抗を覚える社員がいる場合も考えられるでしょう。導入にあたっては適切な社員教育を実施し、システム操作方法およびコンプライアンスの周知徹底が大切です。
ERP導入までの流れ
ERPを導入するには次のような手順で行います。
はじめに行うのは、ERP導入計画の立案です。ERPには多種多様なベンダーおよび製品があり、それぞれ異なる特徴を備えています。導入するシステムの種類によって数ヶ月~1年以上かかることもあるため、計画的な準備期間の設定を行ってください。
次に、前のステップで洗い出した自社の目的に合致するERPのベンダーおよびシステムを選定し、契約を行います。比較のために、カタログやインターネットから情報を集め、自社に適した製品を選択しましょう。
契約が成立した後は、実際にERPを導入する作業に入ります。ベンダーと連絡を取り合いながら、疑問や不安が残らないように進めましょう。
システムの導入を終えたら、続けて社員教育を行う必要があります。ERPの特性を最大限に活かすためには、実際に操作を行う担当者への教育が重要です。業務フローやマニュアルなどを作成し、試行期間を設けることで新システムへスムーズに移行できるでしょう。
ERPの選び方
適切なERPを選ぶには、次の3つのポイントに注目しましょう。
システムの形態や機能は自社の業務内容や規模とマッチするか
ERPの機能や形態が自社の業務内容や規模と合致するかという点は、ERPを選択する際に大切なポイントの一つです。多くの機能を備えたシステムが構築されていたとしても、使いこなせなければ意味がありません。計画の立案段階で何が問題なのかを洗い出し、解決のためには何が必要なのかを十分に検討しましょう。
導入・運用にかかる予算とコストの兼ね合い
ERPの種類や導入方法によって、いつ・どのような予算がかかるのかが異なります。導入後だけではなく、導入前の準備にかかる費用や期間についても考慮する必要があるでしょう。初期費用・ランニングコストを、求める機能および使用期間に照らし合わせ、長期的な視点でのコストパフォーマンスを確認しましょう。
サポート体制が充実しているか
ERP選定の際には、どのようなサポートが受けられるのかという点もポイントになります。セキュリティ対策や、トラブル・災害発生や法改正時のフォロー体制が整っているのかも重要です。企業のITリテラシーのレベルによっては、カスタマーサービスの手厚さにも注目するべきです。事前にERPの内容確認に加え、ベンダーの導入実績や評判・口コミなども調べたうえでERPを選定するといいでしょう。
まとめ
ERPは、企業の経営資源を一括管理し、効率的な業務遂行を可能にするシステムです。適切に導入すれば、人為的なミスやムダな工程を省略することによるコスト削減も狙えるうえ、迅速かつ適切な経営判断を下せるようになります。現代のビジネスでは、限られた経営資源を活用し、いかにして業務プロセスの最適化を行うかという点が求められています。
ERPのメリット・デメリットを把握したうえで自社に適したタイプを導入・運用し、これからの時代を一歩リードする企業を目指しましょう。
NECネクサソリューションズが提供しているClovernet ERPクラウドは、販売管理・財務会計、給与勤怠だけでなく、案件管理とプロジェクト別収支管理まで、オールインワンで管理できる統合型クラウドサービスです。システムを導入すればこれらのバックオフィス業務を効率化します。また、重要な経営データをすべて連携して管理することで、経営状況や資金繰り状況の見える化にも繋がります。無料トライアルや導入前の相談も可能なので、まずはお気軽にお問い合わせください。
Clovernet ERPクラウドの詳細はこちら。