インタビュー 識者が語る情シス課題
New Normalの時代に求められるコミュニケーション環境のあり方
2020年11月
新型コロナウイルス感染症のインパクトは、ビジネスの様々な側面に及んだ。これを機に一般化したテレワークについては、終息後も継続する意向を示す企業が多いようだ。New Normalの時代、コミュニケーション環境もまた見直しを迫られている。特に、クラウドへの移行は大きなテーマだ。IT分野の市場調査やコンサルティングを行うITRの舘野真人氏に、クラウド移行の注意点や注目サービスなどについて話を聞いた。
テレワークを導入した企業の85%が
「何らかの形でテレワークを継続する」
新型コロナウイルス感染症が働き方に与えた影響は大きい。人々のワークスタイルは、以前とは様変わりした。ITRのシニア・アナリスト、舘野真人氏はこう表現する。
「以前は、オンプレミスとオフィス、デスクトップという3点セットがメインの働き方でした。これがクラウド、リモート、モバイルに切り替わった。これまでもテレワークを取り入れている企業はありましたが、あくまでもサブという位置づけでした。いまやテレワークがメインで、サブがオフィスという職場が多くあります」
テレワークシフトは様々な課題を浮き彫りにした。情報環境、コミュニケーション基盤の課題が明らかになった企業も少なくない。テレワークに移行しようとしたものの、ITがボトルネックになりすぐに対応できなかったケースも多いようだ。今回の経験を機に、情報環境の見直しを検討している企業もある。
「New Normalという言葉がありますが、新型コロナウイルス感染症が終息したとしても、以前の働き方に戻ることはないでしょう。今回、経営者を含めて多くの人たちが、テレワークの利便性を実感したからです。ITRの調査でも、テレワークを導入した企業の85%が、今後も何らかの形でテレワークを継続すると回答しています」と舘野氏は話す。
New Normalの時代、情報環境の整備は切実なテーマだ。舘野氏が挙げた3つのキーワードの中でも、とりわけ、基盤としての役割を担うクラウドへの移行が重要なテーマになる。
クラウド移行の注意点としての
コストとセキュリティ、ネットワーク
クラウドへの移行に当たっては、いくつかの注意点がある。舘野氏はまず、IT部門に対してこう提言する。
「おそらく、多くの企業ではIT部門がクラウド移行の実務を担うことでしょう。多くのIT部門は従来、コストやセキュリティを重視する一方で、ユーザーの利便性を後回しにしてきたように見受けられます。クラウドに移行すれば、これまでIT部門が行っていた運用管理の負荷は確実に軽減されます。これを機に、ユーザーの生産性向上を支援するための活動を強化すべきでしょう。それは、IT部門本来の仕事のはずです」
次に、具体的なポイントを考えてみたい。テーマはコスト、セキュリティ、ネットワークである。舘野氏はそれぞれについて次のように語る。
コスト
価格で単純比較するのではなく、導入や運用にかかる工数の削減や、導入規模を適宜拡大・縮小できるといったクラウドの利点を踏まえた上で、コストを評価すべきである。
セキュリティ
ユーザー企業が重視すべきはID管理。セキュリティの高いマンションでも、カギをなくしたら危ない。同じように、クラウドへの入口となるID=カギの管理は非常に重要。クラウドを選ぶときには、多要素認証に対応したサービスを選ぶ。
ネットワーク
テレワークを前提とすれば、付け焼刃の対応では難しく、ネットワークの構造から見直すことが求められる。専門家の知見も借りつつ、テレワークに対応できる次世代型のネットワーク基盤の構想化に取り組むべきである。
期待の高まるコラボレーションツール、
オンラインストレージとデスクトップ仮想化
クラウドシフトを機に、コミュニケーション環境の刷新を考えている企業も多いはずだ。クラウドサービスは急速に進化しており、数年前とは比べものにならないほど使いやすくなったものもある。
電話機をクラウド上のコラボレーションツールに移行
従来は当たり前だった電話機だが、社内チャットを含むコラボレーションツールに切り替えれば、大きなコスト削減効果を得られる。また、ビデオ会議システムの画像をオフにして、電話や電話会議として活用しているユーザーも増えたのではないか。
「顧客や取引先などとの連絡では、いまも電話機が重要と考える企業は多いと思います。しかし、コラボレーションツールの側でも音声機能を強化しており、今後に期待できると思います」と舘野氏。まずは、社内通話から順次コラボレーションツールに移行し、営業など顧客対応の多い部門の電話を最後に切り替える、といった段階的なアプローチも考えられるだろう。
オンラインストレージへの関心の高まり
舘野氏はこう説明する。「業務で求められるコミュニケーションには、フローとストックがあります。フローについてはビデオ会議の普及もあってデジタル化が進みましたが、一方でストックのやり取りは課題として残っています。この課題に対する解決策として、オンラインストレージは必須のツールといえるでしょう。ITRとしても、オンラインストレージ市場は当面は年率15~20%増のペースで着実に伸びると予測しています」。
一部の部門だけでオンラインストレージを利用していた企業が、他の部門、さらに全社に利用を拡大するという動きも見られる。舘野氏の指摘のように、オンラインストレージは情報共有に必須のツールになりつつある。
注目されるデスクトップ仮想化への動き
テレワークが常態化すれば、端末のセキュリティ強化は欠かせない。その対策としても、デスクトップ仮想化は有効だ。
「マイクロソフトは昨年、Windows Virtual Desktopをリリースしました。同社の積極姿勢もあり、対応ソリューションも増えています。今後はパフォーマンスの向上を含め、仮想デスクトップ環境のさらなる進化が期待されます」と舘野氏は語る。
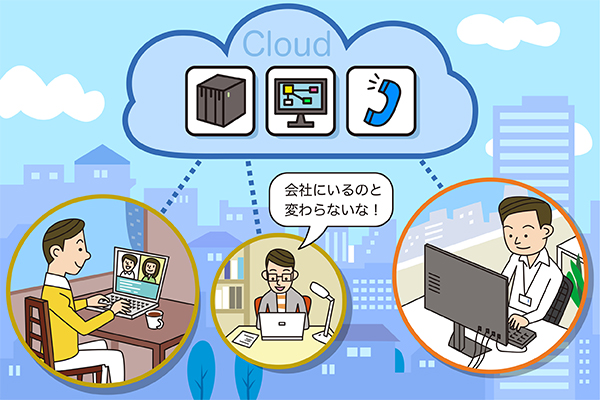
新型コロナウイルス感染症は単に働き方を変えただけではない。社内外のコミュニケーションとつながり方、顧客や取引先との接点のあり方、オフィスの形を含めて企業活動全体が見直しを迫られているようにも見える。
「リアルの場、リアルのコミュニケーションが縮小した中で、デジタルの役割はますます大きくなりました。おそらく、この動きは止められません。オフィス面積を縮小して、その分、デジタル投資を増やすという企業もあります。生産性を高める働き方について、デジタル投資計画を含めて検討してもらいたいと思います」と舘野氏。経営者、IT部門、ユーザー部門が一体になって新しい企業活動の形、新しい働き方を見出す。多くの社員が今回の経験に学んだ現在は、そのタイミングとして最適といえるかもしれない。