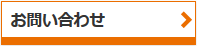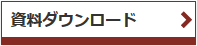コンサルタントのコラム
変わるIT部門
[第2回]アウトソーシングの有効活用
2011年6月(2020年10月改訂)
『変わるIT部門』の第1回では、IT部門の役割変化に対応するための最初のステップとして、業務の優先度を整理する考え方と現状把握の方法について紹介しました。
今回は、自社のIT要員を経営への影響度の大きい業務へシフトするために有効な方法のひとつであるアウトソーシングの活用ポイントについて整理してみます。
事業継続の観点から重要サーバ類のアウトソーシング(ハウジング等)の検討を始めた企業も多いので、少しでも参考になれば幸いです。
電力不足対策としてのデータセンター活用
本コラムの主テーマであるIT部門の役割変化への対応とは動機が異なりますが、震災をきっかけにIT管理業務のアウトソーシングを検討する企業・団体が増えています。
当社でも、24時間365日の停電対策を講じたデータセンターでサービスを提供していますが、震災後は、そのお問い合わせが急増しています。
震災による停電やその後の計画停電により、東日本の広範囲で企業・団体が大きな影響を受けました。 今後の計画停電を回避するためには、各企業・団体が電力使用量の削減目標達成に真剣に取り組む必要があります。
事業インフラとしてのITサービス提供に責任を持つIT部門にとっても電力不足は大きな問題です。
計画停電が実施されなくても、電力需要が供給を超えた場合に発生する計画外の停電は、IT部門のBCPを検討する上で優先度の高いリスクと言えます。
IT機器の停電対策としては、自家発電機の設置が考えられますが、入手までのリードタイム、設置環境、保守や点検等の管理面、燃料の備蓄や災害時の補給等、様々な課題もあります。地震や浸水等の災害対策も合わせて考えるとデータセンターの利用は有効な現実解になります。
緊急対応として重要サーバ類をデータセンターへ移設した上で、IT管理についても、自社要員で行う業務とアウトソーサーに委託する業務とを切り分け、アウトソーシングのメリットを十分に活用することが望まれます。
顕在化したアウトソーシングの課題
電力不足対策としてのITインフラ管理のアウトソーシングは直近の検討課題ですが、将来にわたりアウトソーシングのメリットを享受するためには、予め検討しておくべきポイントがあります。
国内では2000年頃からノンコア業務の効率化やコスト削減を目的としたアウトソーシングが本格化してきましたが、この約10年間でいくつかの問題点も顕在化してきました。
アウトソーシングの主な問題点は下記のとおりです。
- 現場の声がシステムに反映されない
- 契約期間中の事業環境変化に対応できない
- 期待したほどのコスト削減効果が得られない
これらの問題点を参考に、これからアウトソーシングを検討する際のポイントを整理してみます。
コア業務は自社で対応する
アウトソーシングの対象業務の選定には、様々な視点があります。
第1回では、IT部門の業務機能の内、経営への影響度が大きい業務は自社の要員で対応すべき業務と述べました。
例えば、IT戦略策定やそのモニタリング・評価などです。
その他にシステム開発に関する業務機能では、プロジェクト管理、システム企画、システム導入計画、調達管理等も相対的に影響度は大きいと言えます。
また、前述の問題点の内、「現場の声がシステムに反映されない」「契約期間中の事業環境変化に対応できない」という2点については、これがコア業務に関わるITの場合には、競争力を阻害する要因にもなりかねません。
その点では、図1で例示するように、システムライフサイクルのどの業務機能を自社で対応するかは対象システム毎に個別に検討する必要があります。
コア業務に関わるITの場合には、変化への対応スピードや柔軟性確保の視点から自社で対応する領域を決めます。
![[図]](images/cons_column03_02-1.gif) 【図1】システム/フェーズ別に見るアウトソーシング領域(例)
【図1】システム/フェーズ別に見るアウトソーシング領域(例)
非効率な業務をそのままアウトソーシングしてもコスト増を招く
「期待したほどのコスト削減効果が得られない」という問題点については、アウトソーシングする前に業務プロセスの標準化を実施することが必要です。
非効率な業務をそのままアウトソーシングしても、コスト削減にはつながりません。
アウトソーシング活用に至る効果的な流れを図2に示します。
![[図]](images/cons_column03_02-2.gif) 【図2】アウトソーシング活用に至るステップ
【図2】アウトソーシング活用に至るステップ
「現状調査/業務の見える化」では、IT部門としての業務の優先度や自社で対応できる業務の範囲を確認するために、実際にやっている業務の内容や割合、IT要員のスキルや経験等を調査します。具体的な方法については第1回のコラムをご参照ください。
「業務プロセスの標準化」では、業務プロセスの可視化とシステム構成要素の削減を実施します。
業務プロセスの可視化は、アウトソーサーに業務を委託する際には必要な作業であり、業務フローや役割定義の文書化が含まれます。
IT要員の人数が少ないと業務のやり方が属人化して暗黙知になっているケースが多く、まずは現状の業務を第三者に説明できる状態にする必要があります。
その上で、インプットとアウトプット、承認者と実行者等を整理して、不要な作業の廃止、使用帳票類の見直し、IT化等の業務プロセスの改善点を洗い出します。
システム構成要素の削減は、サーバ等のハードウェアやデータベースの集約、サーバOS・データベース・開発言語等の統一が含まれます。
アウトソーシングでは、システム構成要素の数により費用が変わる場合が多いので、事前に可能な限りシステム構成要素を削減した上でアウトソーシングすることがコスト削減のポイントとなります。
また、プラットフォームの統一は、自社で行うコア業務に関わるIT保守や品質管理、委託先管理の効率も大きく左右します。
最後に
今回は、IT部門の人的リソース不足をカバーするためのアウトソーシングの有効活用に必要なポイントの内、対象業務選定の留意点と事前ステップとして重要な業務プロセスの標準化について概略を紹介しました。
この2点と目的の明確化が、アウトソーシングの成功のためには特に重要だと考えます。
また、実際にアウトソーシングする場合には、提供されるサービス品質を維持し、コストパフォーマンスを高めるための管理業務が必要になります。
業務の完全な丸投げを続けていると、「社内の要員に開発・運用スキルが不足し、アウトソーサーを評価できない」という問題が発生する場合があります。
IT部門として将来的にも自社での対応が求められる機能・業務を整理し、中長期での要員育成も合わせて検討することが望まれます。
執筆
NECネクサソリューションズ
シニアコンサルタント 日下部 公
[CISA公認情報システム監査人,システム監査技術者,ITコーディネータ]
- 前編
- 後編