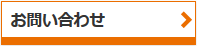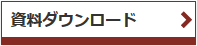コンサルタントのコラム
ITマネジメントレベルの向上
[最終回]弱点の強化~システム運用のレベルアップのために
2010年12月(2020年10月改訂)
はじめに
これまでのコラムでは、ITマネジメントのあるべき姿と評価ポイントを解説した上で、実際に当社のIT部門が、ITマネジメントレベルの向上にどう取り組んだか具体的な事例でご紹介しました。
今回は、「ITマネジメントレベル簡易診断」を実施した結果から、多くの企業が悩んでいると思われる領域について掘り下げて考えてみます。
当社が提供する「ITマネジメントレベル簡易診断」は、IT部門が持つ機能毎(診断対象は9領域)に自社のレベルを定量的に把握することが出来ます。
これまで当社が診断した数十社の結果から、各社共通してレベルの低いのは次の2領域です。
- 事業継続
- システム運用
本コラムでは「システム運用」を取り上げ、その活動のポイントについて考察してみます。
システム運用とは?
情報処理推進機構(IPA)が発行する「情報システムユーザースキル標準(UISS)」において、システム運用は「情報システムの効果の最大化に向けた、情報システム運用の安定的・効率的な実施」だと位置づけられています。
経営に貢献するよう構築された情報システムの効果を最大限引き出すための重要な機能です。
いくらシステムのコンセプトが良く、仕様通りにシステムが構築されていても、システム運用の良し悪しによって“効果が引き出せない”事態も起こります。
システム運用では、以下の様に多くのことを実施することが求められます。
-
システム運用で実施すべきこと
システム管理計画
システム移行
システム管理
資源管理・変更管理
リリース管理
構成管理
問題管理
セキュリティ管理
性能管理
システム利用者対応
運用に関するシステム評価
それぞれ重要な機能ではありますが、システム運用の強化に向けて、まず何から着手していけば良いでしょうか?
このコラムで一貫して申し上げていることですが、マネジメントレベルの向上に欠かせないのは、PDCAサイクルによる継続的改善です。
システム運用を、PDCAサイクルの位置付けで表すと図1の様になります。
![[図]](images/cons_column01_28-1.gif) 【図1】システム運用のPDCAサイクル
【図1】システム運用のPDCAサイクル
システム運用のレベルアップのためには、まずはPlan(システム管理計画)に取り組むことが必要と言えます。
Plan(システム管理計画)でやるべき事はいろいろありますが、特に押さえておくべきマネジメントのポイントを考えていきます。
「システム管理計画」のポイント
この活動の目的は、情報システムへの要求と、その要求を満たすためのコストとのバランスを取った管理を実現するために、「システム管理計画」を立案し、効率的かつ効果的な運用を進めることです。
ビジネスに貢献するためにシステム運用の品質・生産性をPDCAサイクルで改善するのが目指すべき姿です。
システム管理計画は、以下のステップで進めます。
-
【ステップ1】
システム管理要件の定義
-
【ステップ2】
サービス要件の定義
-
【ステップ3】
運用ルールの作成
-
【ステップ4】
システム管理計画書の作成
【ステップ1】システム管理要件の定義
まずは、情報システムの内容や、利用者・システム管理者・ベンダー等との関係を理解し、システム運用管理のための要件を定義する必要があります。
システム運用者の作業範囲を明確にし、システム管理方針を定め、体制や予算を決めて、スケジュールを定めます。
この中で特に重要なのは体制と予算です。
責任が割り当てられ、予算がつかない限り何も始められません。
【ポイント】システム管理の体制
情報システムの効果を最大限引き出すためには、システム運用はシステム構築と同等かそれ以上に重要ですが、システム構築時に比べて、システム運用の体制や予算が明確ではないことがあります。
IT部門やIT環境の規模の大小に関わらず、どのような体制でどれだけの予算でこれからシステム運用を行うかを明確にすることから始める必要があります。
システム管理体制
業務内容やシステム規模などによって体制を決めます。
以下の点に留意する必要があります。
- 運用の責任者が決まっていること
- 予算権限と責任との整合をとること
予算
実績の把握ができるレベルで行うことが重要です。
次の視点での予算化が考えられます。
- システム用途別(基幹系システム、情報系システム)
- コスト分類別(投資コスト、運用コスト)など
【ステップ2】サービス要件の定義
情報システムを運用することは、利用者に対する「ITサービス」の提供です。
利用者に提供するサービスの品質水準を定義することで、システム運用のレベルアップの定量的な目標を持つことになります。
これは、“サービス品質目標の設定”と言い換えることもできます。
【ポイント】サービス品質目標を設定し、モニタリングしていますか?
サービス品質目標を明確にして、公言することは経営者・利用者に対するIT部門の「説明責任」のひとつです。
図2に示すように、「ITサービス」がシステム構成要素を使った、ビジネス(具体的には、経営者や利用者)に対するサービス提供という構造に着目して、サービス品質目標を、3つのレイヤで考えることができます。
-
サービスレベル指標
IT利用者に直接影響を与える指標で、利用者から見たITサービスの品質を計る指標
(例)サービス稼働率、オンライン応答時間、障害による停止件数・時間 -
プロセス指標
システム運用の作業プロセスにおける有効性や効率性を示す指標
(例)平均問合せ解決時間、平均問合せ件数・時間、オペレーションミス件数 -
システムパフォーマンス指標
システム構成要素の可用性やパフォーマンスを示す指標
(例)CPU使用率、回線使用率、ディスク使用量
![[図]](images/cons_column01_28-2.gif) 【図2】サービス品質目標の3レイヤ
【図2】サービス品質目標の3レイヤ
【ステップ3】運用ルールの作成
システム運用において、円滑に業務を処理するために、標準的な判断基準や手順を明確にして運用ルールとしてドキュメント化しておく必要があります。
運用ルールでは、サービス時間や平常時手順、障害時手順、データのバックアップ/保管、申請書・記録の流れ、文書の管理方法などを定めておきます。
【ポイント】運用ルールを文書化して、承認・発行および改訂をしていますか?
運用ルールは、組織として発行しているかが重要です。
筆者が過去にコンサルティングを担当したお客様を考えると、システム運用のマネジメントレベルが低い組織に共通するのは、「運用ルールの整備が出来ていない」ことだと感じます。
ルールが暗黙のままで、責任者も運用者も経験的に業務をこなしているため、改善すべき事柄が見えてこないのです。
継続的改善を阻害する大きな要因になっていると思われます。
以下のポイントを押さえて自社の取り組み状況を把握してください。
- 運用の責任者を定め、責任者が承認しているか
- 運用ルールが関係者に周知されているか
- 運用ルールは関係者がレビューしているか
また、運用ルールや、マニュアル・手順の文書は、常に「現状(システム、人員、手順など)との整合」を意識して最新の状態を維持するよう見直さなければなりません。
一度作って終わりではなく、改訂の状況についても留意してください。
【ステップ4】システム管理計画の作成
システム管理計画の最後に実施するのは、これまでのステップで明確にした、システム管理要件(体制・予算など)、サービス要件を総合的にとりまとめ、システム管理計画書を策定することです。
【ポイント】システム管理計画は、文書化され、関係者に開示していますか?
外部向けのシステム管理計画(IT部門以外の部門向け)
サービス要件に関するシステム管理計画は、「利用者向けサービス説明書」等の形で文書化し、システムのユーザに開示して、目的・目標を共有することが大事です。
経営者・利用者に対してシステム運用の説明責任を果たす第一歩になります。
内部向けシステム管理計画(IT部門内部向け)
情報システムを運用するためのシステム管理計画は、「システム運用計画書」や「IT部門の事業計画書」等の形で文書化し、運用担当者に開示してIT部門の役割や責任を共有することが必要です。
まとめ
システム運用は、正常な状態を維持して当然という認識を持たれることが多く、その担当者は、日々の業務で達成感を得にくい状況になりがちです。
システム運用の社内事例を紹介した第3回のコラムでも、最後は人の意識が非常に重要だと結論づけています。
システム運用のマネジメントレベルを上げることは「人」を育成するということです。
「システム管理計画」は、高いモチベーションをもってシステム運用ができる人材育成の最初の一歩とも言えます。
『システム運用がちゃんとできてないなぁ・・・』とお悩みの組織の方は、是非、「システム管理計画」から着手してみてください。
これまでにご紹介してきたコラムの内容が読者の組織における「ITマネジメントレベルの向上」に少しでも参考になれば幸いです。
今回をもって「ITマネジメントレベルの向上」に関するコラムは一旦終わらせて頂きます。
最後までお付き合い頂き、誠に有難うございました。
執筆
NECネクサソリューションズ
コンサルタント 松吉 賢幸
〔公認情報システム監査人(CISA)〕