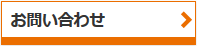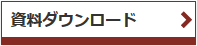コンサルタントのコラム
正しいIT戦略のつくりかた
[第2回]現場の問題意識から方針を作る
2010年9月(2020年10月改訂)
前回は、「正しいIT戦略とは、経営目標や事業目標の達成に寄与するものであり、その基本構造は、目的・方針・方策のセットである」ことを述べました。
今回は、現場の問題意識から『重要課題』を抽出して、IT戦略の「方針」に仕立てる方法について考えてみます。
現場から問題意識を集める
まずは素材として、現場の人々が日常的に抱いている問題意識を集めることになります。E-mailや個別ヒアリングがよく利用される手段ですが、近頃ではWebシステムを使ったアンケート収集などにも使い勝手の良いものがあります。
できるだけ多くの関係者から広く意見を募るのが良いでしょう。
このときに重要なのは「現在のITシステムに関する問題だけを集めてはいけない」ということです。
「次期ITシステムの構築にあたり問題点をお寄せ下さい」
では、集まってくる意見のほとんどが
「○○システムは使いにくい」
「応答が遅い」
「○○機能が欲しい」
などの現状システムに関する、表層的な問題意識となってしまいがちです。
望ましいのは
「皆さんが日々業務を遂行されているなかで、ここがこうなったらいいなと思われることをお書き下さい。ITシステムに関係しているかどうかは問いません。」
といった風の表現でしょう。
集めた問題意識を分類、集約する
分類する
多くの問題意識があつまったところで、分類を行います。
まずはITシステムに関するものと、そうでないものに分類します。
次にITシステム関係はサブシステム別に分類し、非ITシステム関係は業務別に分類します。このときに分類の区分はそれぞれに7種類前後にとどめて、どれにも当てはまらないものや全般的な問題意識は「その他」という分類に入れておくと良いでしょう。
| 業務関係 | A1:経理 | ITシステム関係 | B1:会計システム |
|---|---|---|---|
| A2:総務庶務 | B2:総務庶務システム | ||
| A3:購買 | B3:仕入システム | ||
| A4:工場 | B4:生産システム | ||
| A5:物流 | B5:販売システム | ||
| A6:営業 | B6:情報系システム | ||
| A7:経営 | B7:ITインフラ全般 | ||
| A9:その他 | B9:その他 |
集約する
分類ができたら次は集約です。
まずは分類された問題意識から、単なる願望や思い込みに該当するものに削除マークをつけます。
ここで大切なのは「不平や不満やグチ」であると言う理由では削除しないで、あくまでも「問題意識として根拠がない」ものや「実現性が極めて薄い」ものを削除することです。
なるべく多くの関係者に削除対象となったものの妥当性をチェックしてもらうことも大切です。
削除が済んだら、よく似たことを表現しているものをグループ化します。ひとつしかないものはそれでグループとみなします。
それらのグループを集約した表現を考え、集約された問題とします。
このときに「○○○が(△△△)ない」といった否定形の表現に統一します。
集約された問題を解決するような表現、すなわち「○○○を(△△△)する」という肯定形(というか前向き)の文章を考えて「課題」とします。
集約した例| No. | 課題 | 問題(集約) | No. | 問題意識(原文) | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | お客様の問い合わせに、適切に対応する仕組みを構築する | お客様の問い合わせに適切に対応できていない | 25 | お客様からの問い合わせに対して、素早い対応ができない | A9 |
| 48 | 問い合わせに適切な回答ができない | A9 | |||
| 137 | お客様からの要望が複雑になっている | A9 | |||
| 151 | 誰もが問い合わせに対応できるわけではない | A9 | |||
| 17 | お客様の変化するニーズをとらえて、商品に反映させる | お客様の変化するニーズを満たしていない | 12 | 顧客満足度が下がってきている | A9 |
| 101 | お客様のニーズの変化に、当社の商品が追いついていない | A9 |
課題から重要課題を選択する
ここまでの作業で多くの課題(解決するに値する問題)が見つかったと思います。
ですが、すべての課題に対応することは無理があります。限られた資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を有効に使うためにも、優先的に解決する課題を選択することが必要です。
前回のコラムで「重要課題」を以下のように定義しました。
【重要課題】
企業には様々な課題があるため、上位目的(企業理念・ビジョン・経営戦略)との整合性が高い課題を「重要課題」として集中的に解決する事が合理的である。
戦略の「方針」に相当するテーマ。
重要性・有効性・具体性などを尺度として課題から抽出する。
重要課題を選択する作業のポイントは2つです。
- 上位目的(企業理念・ビジョン・経営戦略)との整合性のチェック
- 重要性・有効性・具体性のチェック
これらのポイントを押さえたワークシートの例を示します。
| 上位目的(経営戦略) | No. | 課題 | 重要性 | 有効性 | 具体性 | 合計 | IT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ・顧客満足の向上 | 16 | お客様からの問い合わせに、適切に対応する仕組みを構築する | 2 | 1 | 2 | 5 | ○ |
| ・顧客満足の向上 ・新商品の開発 |
17 | お客様の変化するニーズをとらえて、商品に反映させる | 2 | 2 | 1 | 5 | △ |
このワークシートでは、課題ごとに関連する上位目的(この例では経営戦略)をすべて記入し、課題ごとに重要性・有効性・具体性に得点を与えています。
また、課題にはITによる対応が有効なもの、ITが関係する可能性がありうるもの、ITとは関係が無いものがありますので、それぞれ○△×を付けておきます。
多くの上位目的に関係し、かつ、得点合計の高い課題を「重要課題」として選択することになります。そのなかでIT欄に○と△がついているものがIT戦略の「方針」となる重要課題です。
ITに関係ないと判断された課題でも、重要課題であるかぎりは取り組む価値があるものですので、IT戦略企画プロジェクトの報告書に「ITに関係しない業務改革テーマ」として記載しておくべきです。
今回のポイント
- 現在のITシステムに関する問題だけを集めてはいけない
- 問題の分類コードはIT関連・非IT関連ともに7つ前後とする
- 問題は否定形、課題は肯定形で表現すると良い
- ITに関係ない重要課題もIT戦略企画プロジェクトの報告に盛り込む
次回は、IT戦略における方針(重要課題)についての方策を導き出す方法について考えてみます。
執筆
NECネクサソリューションズ
シニアコンサルタント 冨澤 雅彦
[日本TOC推進協議会 正会員、日本UML推進協議会 BPMN研究会副主査]
本コラムに関連するコンサルティングサービス
- ITシステム企画サービス
ツボを押さえたシステム企画を立案し、次期ITシステムの投資対効果を最大化します。