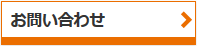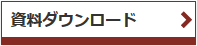コンサルタントのコラム
10年先を見据えたその第一歩としてのIT中期計画を! 第1回
2021年9月
1. ITへの関心が劇的に変わった?
1-1 COVID-19で経営者や従業員がITに関心を持った?
世の中ではCOVID-19でリモートワークが増えた、働き方が変わった、とか言っているが本当だろうか?お客様を見ても7~8割は出勤して仕事をしていらっしゃる。そのうち半分ぐらいは遠隔コミュニケーションであるが、もう半分は今もフェイス・トゥー・フェイスで商談をしている状況である。
なかなか変わらない日本人の働き方。政府は在宅勤務率7割と言うが東京でもせいぜい2~3割という現実がある。IT業界としては2~3割と言っても大きいのだが…
現実には工場や店舗には人が出ている。バスの運転や整備、ホテルの接客やバックヤード、倉庫での入出庫やトラックの運転、現場機器のメンテナンス作業など、出なきゃいけない仕事は山ほどある。一部の営業やスタッフには「家ではなかなか仕事ができない」と言って出勤している人もいる。そう意味では2~3割というのは妥当な線なのかもしれない。少しでも現場の動きが変わる何かが必要だということだろう。
ただITへの関心は少し高まったのではないか。ITが変えていく未来を少しは感じ取ることができた方も多いのではないかと思う。
1-2 ITで躍進するアジア、取り残される日本
私が働き始めて35年、変わっていないと言えば、随分と減ったがハンコや稟議書はもとより、必ずフロアにある行先板、いまだに名刺に番号が表記されるFAX、携帯電話があるのになぜか使っている音声電話(PBX)、「やっぱりA3の紙で全部見られるといいんだよね~」という紙の会議資料など、信じられないくらいに沢山ある。
4~5年ほど前に中国の方と名刺交換をした際に「まだFAX使っているの?」と笑われ、いや日本ではまだ大切なツールなのだ、と恥ずかしい言い訳をしたことがある。ちなみにFAXを一番使っているのは米国で、次いで日本、ドイツ、フランス、イギリス。以前から業務で活用してきた国では変えていくのはなかなか大変だ。
ただ20年前からずっと続いている業務プロセスは本気で見直した方がいい。コミュニケーション手段はもとより、ずっと変わらない(変えられない)基幹業務システムや経理システム、人事システムなど、ビジネスプロセスが変わらないということは進化していないということ。
あなたは20年前、何をやっていましたか? 同じことをやっていないか点検をしたほうがよいだろう。
2. 今までのITでいいのか?
2-1 競争相手は何を考え、何をしてくるか
これからの10年後、20年後を見据えて考えると、ITを活用せずに生き残っていける企業はない。
仮に今、競争相手が何をしてきたら嫌か?
顧客データを蓄えて、いまのお得意先に食い込んでこられたら…
無人店舗を一斉展開してコスト競争を仕掛けてきたら…
AIを使って圧倒的な品質管理を行って、得意先を取られたら…
5年後、10年後の競争環境はどのようになっているか?あまりのんびりとはしていられない。
2-2 10年後、サーバを買う企業ってある?
10年後にはサーバを購入するのはごく限られた用途になっている。工場内をリアルタイムで制御したり、店舗内のIoT(注1)端末データを扱ったり、といった機器以外はクラウドに移行していくだろう。
さらにクラウド移行したあとどうなるか?
クラウド上にいちいちサーバを用意する必要性はなくなり、アプリケーションもマイクロサービス化して、ローコード・ノーコード化もどんどん進んでいくだろう。
もう一部では始まっているサーバレス化、その時クラウドの本当の力が発揮される時代となるだろう。今来ているクラウド化の波に乗り遅れずに。
2-3 圧倒的なネットワークパワーの増大
クラウドシステムの進展を支えたのは、圧倒的なネットワークパワーの増大である。2000年にはフレッツADSLが提供開始、2010年にはドコモがLTEサービスを開始、それが今や5Gといったネットワーク技術の進展なしでは、今日のITの発展は語れない。
またそれは今後の10年も同じ。2030年には6Gが広まっていることだろう。このクラウド+ネットワークの進展をどうビジネスに活かしていけるか、真剣に検討していかなければいけない。
もしかすると10年後には企業内にLANはないかもしれない。
2-4 あなたの会社のBCPは大丈夫?
さて皆さんの会社のBCPはどうなっている?
今はBCP見直しの時。いまだに対策本部会議をリアルにやりますか?
深夜や休日、トップがバカンスを楽しんでいる時、そのBCPは役に立つだろうか?
そのBCPは本当に機能するかどうか、ITを活用したBCPに見直しをして、災害を想定した訓練を行い、実効性のあるBCPにしていくことが求められている。
いち早い決断と対応をするために、自動化とオンライン化を進めよう。
2-5 DX(注2)はバズワード?
「DXはバズワードか」とよく聞かれる。個人的にはバズワードかと思う。
ただ世界的レベルのIT経営ができないと、日本の国際競争力がますます低下することは間違いない。そういう意味で総論としての「DX」という言葉には意味があるかもしれない。
「DX」は本来、個々の企業で「違うもの」だ。昔、社長が「SISを買ってこい」と言った話と(50代じゃないとわからないか…)、全く同じ話である。
だから企業内では「DX」という言葉を使って議論せず、新しい競争力領域をどう設定し、それをITでどう実現していくか、といった議論をしてほしい。
2-6 ITにとって外の世界は危険がいっぱい
この1年で「PCを全社員に持たせたい」という話も多くの企業から聞いた。自社のITを閉じた世界にはしておけない、また行政も医療も同じである。
長らくセキュリティは閉じた企業内のネットワークを守るものであった。ところがそれを破って入ってくる脅威が増加するとともに、PCを持ち出し、自ら危険な世界へ出ていく事態を迎えている。そこでゼロトラストやらパスワードレスやらといった新たなキーワードが出てきている。
セキュリティは永遠の課題、3年前のセキュリティ対策は捨てた方が良いかもしれない。セキュリティだけは最新の情報収集を絶やさないようにするとともに、ここには費用を惜しまず、きちんと対策しよう。
「PCを全社員に持たせたい」という願いは、思いのほか高くつくことを知ってほしい。しかしぜひ実現させて欲しいと思う。
2-7 求められるのは基幹システムだけではない、広がるIT部門の役割
今までのIT部門は会社の基幹業務システムのお守りをしてきた部分が大方を占めてきた。しかし今、基幹業務システムと現場情報システムの比重変化が起き始めている。現場に関わるIT化を避けて通るわけにはいかない。しかし変わらない体制でそれをどう捌いていくか。
採用や人事ローテーションの中で人を確保していくことや、自社で賄う部分と標準化・共通化していく部分を整理して、標準化・共通化できる部分をアウトソーシングしていくことも検討が一層必要と思う。
またDXで求められるのはIT部門と現場とが一体となって問題解決をしていく姿。現場と一体になったプロジェクトや、人事ローテーションも意識していきたい。
- 注1:IoT: Internet of Things(インターネット・オブ・シングス)
“モノのインターネット”と呼ばれ、自動車や家電など、身の回りの様々なモノをネットワークで接続し、得られたデータをより便利に活用するという考え方 - 注2:DX:Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること(経済産業省「DX推進ガイドライン」より)