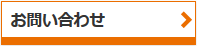IoT
モノづくりIoTソリューション(リードタイムの短縮) 第6回
モノづくりIoTについて(2) ~基本的な考え方~
2017年11月
モノが語るよい流れ創り
前回、モノの「正確な位置情報」を捉えることが可能になったと説明しました。例えば、UbisenseのRTLS(Real Time Location System)では、棚にあるモノを上の段から下の段に移動(15cm以上)した実績も分かるようになります。また、MojixのStarSystemでは、パッシブRFIDで200m先の位置情報を1~3mの精度で検知することが可能になりました。
![[図]モノが語るよい流れ創り](images/column06_1.gif) モノが語るよい流れ創り
モノが語るよい流れ創り
工場では、定置・定品・定量で整理整頓されていると思います。モノづくりの現場では、場所と行動(保管、移動、段取、作業 等)が定義されていますので、モノの位置情報によって、各種実績情報は全て収集できます。例えば、部品が入荷場に届いて、検査待ちの置き場に置かれ、検査場に入って、出て、部品倉庫に入って、出庫されれば、「入荷時間」「検査待ち時間」「検査時間」「移動時間:検査-部品倉庫」「部品保管時間」が分かります。
収集されたデータの関連は、現品票の情報(識別子:ロットNo+品番、製番+品番 等)をもとにモノの流れを構造化することができます。モノの流れが見えることによって、淀みを発見することができます。倉庫での保管、段取り時間、作業時間、仕掛時間 等、スムーズに流れていない箇所を特定することができます。
モノづくりIoTの基本的な考え方
モノづくりIoTの目的は、単位時間当たりのキャッシュの最大化です。いかにして短時間でモノを金に換えるがポイントになります。そのためには、モノの流れのデジタル化(事実化)と、流れの分析が必要になります。
モノの流れを示すには、そのモノをトレースできる「識別子」と、「位置情報」「時刻情報」が必要です。モノ 1つ1つを識別できない場合(モノが小さく、ロット単位に流れる場合)は、加えて、「数量情報」 が必要になります。
モノの流れ=識別子(ロットNo+品番、製番+品番 等)+位置情報+時刻情報(+数量情報)
良い流れを創るには、「モノの流れ」が基礎情報です。次にモノの流れを阻害している構成要素、(場所別の)「設備」や、「工具」「人」 などから、それらの稼働情報(時刻情報+各種事実情報)を収集します。これらの情報をもとに、場所と時刻を突き合わせ、淀みをつくり出しているムダを発見し、その原因を排除します。この時、自工程だけでなく、前工程の設備や作業により、トラブルが発生することも少なくありません。前後工程も含めて原因を遡及します。
モノの流れの見える化により、ムダを削除し、流れるスピードを早め、流れる距離を短くし、リードタイムを短縮します。既に、現場改善活動を行っている場合は、モノづくりIoTによる事実情報によって、よりパワフルに推進することができます。現場では、不良や、納期遅れは管理されていますが、リードタイムは測定されていないので、待ち時間や、手直しによる遅れは見逃されています。(実は現場では、何故、遅れたのかさえも分かっていないこともあります)
モノの流れは、最初から全ての流れを対象にするのではなく、最初はボトルネック工程を含むラインや、特定の製品に絞って行うようにします。次に、設備、作業者、工具など、重要性の高い順に収集していきます。
補足
良い流れを創るには、淀みを発見し原因を取り除くことが重要ですが、現場ではモノの流れを止めないことも非常に重要です。設備の故障や、欠品などのトラブルによって、モノの流れが止まることは避けなければなりません。その為には、今、モノが流れているのか、停滞しているのか、設備が稼働しているのか、工場の事実情報をリアルタイムに見える化する必要があります。
大手製造業では、グローバルに複数の(大きな)工場の稼働状況を監視する必要があるのでリアルタイム性を強く要求されます。それに対して、中堅製造業では、現場が十分に見える範囲なので、パトランプや、あんどん、生産進捗ボード 等を使って現場で対応することが多いため、リアルタイムな監視の必要性は低いのかもしれません。
![[図]モノの流れの収集について](images/column06_2.gif) モノの流れの収集について
モノの流れの収集について
モノの流れの収集は、「モノが語る」です。モノが、どの位置にあるのかによって、その状態を収集します。
まず、場所に、そのモノに対して行われる動作を定義します。例えば、倉庫に「保管」、通路に「移動」、設備横に「段取、手持ち」、作業場所や、設備に「正味作業」といったように設定します。良い流れを創るには、スムーズに流れる道筋が必要になります。道筋は、場所をつなぎ合わせて構成されます。但し、全ての場所を定義する必要はありません。(抜けても構いません)また、幾つかの場所をまとめて、1つの場所として定義しても構いません。例えば、穴抜き、曲げの2つの設備を1つの場所として、板金加工という場所を定義します。全ての場所を詳細に、高い精度で、リアルタイムに捉える必要はありません。リードタイム短縮に効果的なところから、スモールスタートで始めることをお勧めします。
モノの流れの収集イメージは、定義した場所に大きなボタンがあると考えて下さい。モノが入ってくると、そのモノが、ボタンを押します。この時、その場所の動作が開始されます。動作が完了し、そのモノが離れるとボタンが解除され、終了実績が収集されます。ロット単位に流れる場合は、全てのモノが離れるまで、都度、終了実績が収集され、その場所の仕掛として管理されます。(10個ロットで開始、終了5個/仕掛5個、終了5個で完了)基本的な実績データはこれだけです。複数の部品の投入や、分作などは自動的に構造化してモノの流れを表示します。
モノづくりIoTでは、部品表や、工程手順 等のマスタ情報を整備する必要はありません。また、作業計画や作業指示 等の計画情報も必要ありません。現場でのモノの流れの事実情報のみを収集、事実情報の分析を行います。また、こうすることにより、上位の生産管理システムや、ERPシステムから独立して、容易に導入することができます。
モノづくりIoTの基本的な考え方を紹介しました。
次回は、モノづくりIoTによる「ムダのあぶり出し」について説明します。