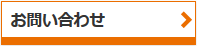IoT
モノづくりIoTソリューション(リードタイムの短縮) 第11回
利益視点からキャッシュ視点へ(2) ~効率とリードタイム短縮~
2018年3月
利益視点からキャッシュ視点へ
今回は、第10回からの続きで、「利益視点からキャッシュ視点へ」の続編について説明させて頂きます。
まず、第10回でお話ししたことを整理します。
![[図]付加価値(キャッシュ)の拡大](images/column11_1.gif)
1. リードタイムを短縮することにより、モノの流れは速くなります。
リードタイムが1ヶ月から1週間になれば、飛躍的にキャッシュの回転率は良くなります。ここでのリードタイムは、個当たりリードタイムを考えると分かり易くなります。モノ1つに注目して、そのモノの部品入庫~製品出荷までの時間です。このように考えると、まとめ発注、まとめ作りすると、非常に時間が掛かることが分かります。
個当たりリードタイムを短縮するには、小ロット化が有効です。(究極は1個流し)この時、小ロット化による段取替えなどの非正味作業時間の短縮が重要になります。
2. リードタイムを短縮することにより、その時点で管理する仕掛数が減少します。
その結果、管理工数を削減することができます。リードタイムが1日であれば、その時点で管理する対象は、1日分です。リードタイムが1週間であれば、その時点で管理する対象は、1週間分になります。
リードタイムを短縮することにより、管理工数を削減し、間接工数から直接工数への変換が可能になり、固定費の効率化が図れます。さらに、将来の需要変動への対応力もあげることができます。
3. リードタイムを短縮することにより、全ての商品は商品価値を高めることができます。
短納期化は他社との差異化を実現します。
リードタイム短縮により、1.モノの流れが速くなり(キャッシュの回転率が上がり)、2.管理工数が削減され、将来の需要変動に対応でき、3.商品価値をあげることができます。これらにより、単位時間当たりの付加価値(キャッシュ)を拡大できることを前回、説明しました。
効率とリードタイム短縮
現場では、様々な改善活動が行われています。この時、現場での評価指標が非常に重要になります。第8回 モノづくりIoTについて(4) ~現場力の見える化~ の中で、「現場力=正味作業時間/リードタイム(NCTR:Net Conversion Time Raito)」を紹介しましたが、効率とNCTRについて利益とキャッシュの視点で考えてみたいと思います。
![[図]効率とNCTRについて](images/column11_2.gif)
一般に、工程や、ワークセンタの評価指標として、よく使われるのは、「稼働率」です。高価な設備を導入すると、「設備の稼働率を上げろ。遊ばせておくな」と管理者からの指示が飛びます。勿論、稼働率を上げることが全て間違いではありませんが、稼働率を上げるために、「先食い」をすることは、大きな過ちです。
単位時間当たりの稼働率を上げる(生産数を増加させる)と原価は低減され、(見た目の)利益は拡大します。この時、「先食い」をしていたらどうなるでしょうか?キャッシュは早く出ていくことになりますので、キャッシュは悪化します。更に、「先の先の先食い」をしたらどうなるでしょうか?内示や、需要予測が外れて売れ残ったら、更にキャッシュは悪化します。
「先食い」は、「設備を稼働させないことは悪いこと」「忙しく働いていないことは悪いこと」という誤った思い込みから生まれます。これを防ぐためには、現場力(NCTR)を有効に活用する必要があります。工程のNCTRは、「自工程の正味作業時間/自工程の着手~次工程の着手(リードタイム)」になります。これは、余計な在庫を作らず、後工程に同期して自工程の作業を開始することを示しています。
「稼働率」は、生産数の最大化を目指した利益視点の指標であり、「工程のNCTR」は、回転数の最大化を目指したキャッシュ視点の指標と言えます。稼働率の向上は、十分な需要がある時、ボトルネック工程である時に有効であることを理解しておく必要があります。また、全体の需要と設備の処理能力のバランスを取ることが重要です。
例えば、専用設備の場合は前後工程が見えますので、需要と処理能力のバランスはとり易いのですが、熱処理や、表面処理のような汎用設備の場合は、色々な仕掛品を一度に処理できますので、バランスが見えにくく「先食い」が起こりやすくなります。このような場合、「稼働率」だけではなく、「工程のNCTR」を見ながら、後工程との在庫を最小にするように全体のバランスを取ることが必要です。
投入工数について
次に、投入工数について考えてみます。
付加価値は、一定期間の売上から得られたキャッシュから、外部購入費として支払ったキャッシュを差し引いたものが付加価値です。従って、キャッシュアウトからキャッシュインまでの期間が、付加価値を生むリードタイムになります。しかし、キャッシュアウトからキャッシュインまでの期間を測定することは一般的に困難です。(キャッシュは紐付けられません)
そこで、モノの流れに注目して、モノの流れを早めることにより、付加価値向上を目指していきました。しかし、モノが動かない製造業は沢山あります。例えば、大型のエンジンや、工作機械、輪転機など、造船業や、建設業、システム開発なども同様です。
このような業界で、価格交渉が行われた時、どのように考えるでしょうか?
例えば、30人 × 6ヶ月かかるプロジェクト(180人月)に対して、1/3の原価低減を要求された場合、どうでしょうか?
案1:投入する人員を、30人 → 20人にし、120人月を実現する
案2:プロジェクト期間を、6ヶ月 → 4か月にし、120人月を実現する
案1と案2のどちらを選択しますか?
![[図]投入工数の削減(原価低減)](images/column11_3.gif)
原価低減の観点からみると、案1も、案2も同じです。しかし、キャッシュ視点で考えた時は、どうでしょうか?
案2は4ヶ月後に、120人月に相当するキャッシュを得ることができます。案1は6ヶ月後です。勿論、案1で削減した10人×4ヶ月=40人月に相当するキャッシュを得ることができるかもしれませんが、確定ではありません。
案1で削減された要員は、どんな要員でしょうか?プロジェクトリーダーは削減対象にはならないと思います。サブリーダークラスは対象になるかもしれませんが、ほとんどはプロジェクトメンバーだと思います。従って、削減対象のメンバーで新たなプロジェクトを遂行することは難しいことが予想されます。
案2では、4か月後にはプロジェクトリーダー、サブリーダーも解放されるので、直ぐに別のプロジェクトを担当することができます。ポイントは、「ボトルネックであるプロジェクトリーダー」の回転率を上げることです。
案1では、進捗遅れが発生した際、工数オーバーとともに、納期遅延が発生します。案2では納期遅延は発生しません。更に、リードタイムが短縮できれば、お客様に対する提供価値を上げることができます。
最後に、人材育成の観点から見てみましょう。新人は、できる限り多くのプロジェクトに参加する方が良いと思います。プロジェクト期間が短くなれば、より多くのプロジェクトに参加することが可能になります。また、プロジェクト期間を短縮するために、プロジェクトメンバー全員で議論することは非常に多くのことを学ぶことができます。
多くの場合、投入する人員を削減する「案1」を選択すると思います。「効率を上げる」と言った時、最初に思いつくのは「投入人員の削減」です。これは、プロジェクトは不確実であり、予期せぬ事が発生した時、お客様との納期の調整よりも、投入人員の調整(残業、増員)の方が容易だと考えているためです。しかし、実際には、プロジェクト期間を見積もる際には、大きなサバ(バッファ)を見込んでいる場合が多いので、プロジェクト期間を短縮することの方が、容易であることが少なくありません。
一般に、プロジェクト期間は、一度、設定したら変更することが困難であるため、重要なプロジェクト、金額の大きなプロジェクトになればなるほど、責任感の強いプロジェクトリーダーであればあるほど、十分なバッファを見込んで期間を見積もっています。(実は多くの大きなサバがある)
全ての業種、業態において、付加価値を向上するためには、まず、リードタイム短縮、キャッシュ視点で考えて下さい。効率を上げることがリードタイム短縮や、キャッシュの増加につながっているかどうか、確認することが重要です。