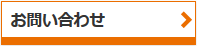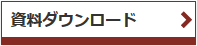コンサルタントのコラム
在庫のはなし
[第3回]DBM(ダイナミック・バッファ・マネジメント)
2011年3月(2020年10月改訂)
DBM(ダイナミック・バッファ・マネジメント)について
DBMは、日本でもベストセラーとなったビジネス小説「ザ・ゴール」で知られる、エリヤフ・ゴールドラット博士が提唱する制約理論の中で、在庫削減のソリューションとして開発された方法です。
2009年に発刊されたビジネス小説「ザ・クリスタルボール」(ダイヤモンド社刊)の中で、小売業で店舗在庫の削減を実現するための手法として分かりやすく書かれています。
かなり挑発的なアオリが本書のオビに書かれていますので引用しておきます。
売れ残るリスクを抱えてまで在庫を持つべきか、それとも売り逃すリスクがあっても在庫を減らすべきか。 「在庫を大幅に減らしながら、利益を上げる」――常に市場の変化にさらされ、競争の激しい小売ビジネスの “限界なき可能性” を示す。
『ザ・ゴール』が世界のものづくりの世界を変えてしまったとするなら、本書『ザ・クリスタルボール』は、小売業のあり方を変えてしまったと後世語られることになるだろう。
従来の在庫管理手法との相違点
DBMでは、在庫を需要の不確実性に対する緩衝(バッファ)として考えているため、アイテムごとの目標在庫量を「バッファ」と呼びます。
そして、発注日に実在庫量がバッファより少ない場合、その差が発注量となります。
DBMが従来の在庫管理手法と大きく異なる点が、そのバッファを増減させるロジックにあります。 前述したようにここでは需要の予測を行いません。
基本的な管理方法は以下の通りです。
- バッファを三等分し、上から緑、黄、赤のゾーンに色分けする。
- 発注時点での実在庫量がどのゾーンにあるかチェックする。
- バッファ緑またはバッファ赤の場合、連続して何回目かをカウントする。
- バッファ緑の連続回数が規定値に達した場合はバッファを減らす。
- バッファ赤の連続回数が規定値に達した場合はバッファを増やす。
- 実在庫量がバッファより少ない場合、その差を発注量とする。
とてもシンプルですが、これだけがDBMの基本的な管理方法です。
目標在庫のコントロール方法
![[図]](images/cons_column01_34-1.gif)
![[図]](images/cons_column01_34-2.gif)
事前に決めておく値(パラメータ)として、初期のバッファ量、バッファを増減させるためのしきい値(緑の連続回数と赤の連続回数)、バッファを増減させる割合、が必要となります。
DBMのパラメータを次のように設定した場合のバッファの増減を表したものが以下の図です。 初期のバッファ量:平均日販の20日分、赤の連続回数:3回、緑の連続回数:5回、バッファの増減:増減ともに30%。
![[図]](images/cons_column01_34-3.gif) バッファ増減の例
バッファ増減の例
この図を見て直感的にわかるのが、バッファの量がダイナミックに増減しながら、発注日になるべくバッファ黄の状態となるように収束していきます。
もちろん需要の変動に対応してバッファも変化しますので、季節変動やはやりすたりにも(多少のタイムラグはありますが)対応できることになります。
DBMの効果
単純なロジックにしたがってバッファを増減させるDBMですが、これを適用した場合の在庫削減効果には目をみはるものがあります。
世界での事例では在庫削減率40%~50%という実績が報告されていますし、この方式と相性の良いアイテムでは70%を超える在庫削減効果が期待できます。
一方で、DBMと相性の悪いアイテムも存在します。
その場合でも、数%程度の在庫削減効果と発注作業の省力化が期待できます。
<ちょっと一言>
「ゴールドラット・マーケティング・グループ事例集」というキーワードで検索すると、TOCによる多くの改善事例と改善効果が見つかるでしょう。
執筆
NECネクサソリューションズ
シニアコンサルタント 冨澤 雅彦
[日本TOC推進協議会 正会員、日本UML推進協議会 BPMN研究会副主査]