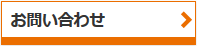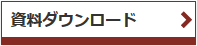コンサルタントのコラム
在庫のはなし
[番外編]DBM(ダイナミック・バッファー・マネジメント)の適用のポイント
2012年9月(2020年10月改訂)
第3回でDBM(ダイナミック・バッファー・マネジメント)についての話をしました。
今回は、入荷リードタイム(注)が比較的長い1週間以上の場合にDBMを用いる際の注意点および、適用する上でのポイントについて述べていきたいと思います。
発注間隔より、入荷リードタイムが長い場合
入荷リードタイムが長い場合、往々にして発注間隔が入荷リードタイムより短くなります。この場合に、どのようなことが考えられるでしょうか?
発注間隔が2日で月曜、水曜、金曜に発注され、入荷リードタイムが3日の商品があった場合、月曜の発注分は木曜に入荷されます。
月曜日に、30個の商品を発注した場合、次の発注日の水曜日はまだ、発注した商品が入荷されていません。発注は行なったが、未入荷の状態(発注残)は30個となります。
つまり、発注間隔より、入荷リードタイムが長いと発注日に発注残がある状態で発注量を決める必要がでてきます。
発注残がある場合の発注量の求め方について
まずは、第3回で説明したDBMにおける発注量の求め方について確認します。
- バッファを三等分し、上から緑、黄、赤のゾーンに色分けする。
- 発注時点での実在庫量がどのゾーンにあるかチェックする。
- バッファ緑またはバッファ赤の場合、連続して何回目かをカウントする。
- バッファ緑の連続回数が規定値に達した場合はバッファを減らす。
- バッファ赤の連続回数が規定値に達した場合はバッファを増やす。
- 実在庫量がバッファより少ない場合、その差を発注量とする。
発注残がある場合は、2と6の実在庫量のそれぞれに発注残を加味する必要があり、下記のようになります。
- バッファを三等分し、上から緑、黄、赤のゾーンに色分けする。
- 発注時点での実在庫量+発注残がどのゾーンにあるかチェックする。
- バッファ緑またはバッファ赤の場合、連続して何回目かをカウントする。
- バッファ緑の連続回数が規定値に達した場合はバッファを減らす。
- バッファ赤の連続回数が規定値に達した場合はバッファを増やす。
- 実在庫量+発注残がバッファより少ない場合、その差を発注量とする。
発注残を考慮して発注量を決定しないと、以下の図のように、余分な発注を行うこととなり、また、バッファの色の判定も誤ってしまいます。
![[図]](images/cons_column01_51_1.gif) 発注残と、バッファ判定、発注量の関係
発注残と、バッファ判定、発注量の関係
安全余裕について
日々の売上のばらつきが大きい商品の場合は、安全余裕を持つかどうか、または、いくつ持つかどうかの検討も必要になります。
特に、入荷リードタイムが長い1週間以上の商品の場合は、ばらつきの影響を無視できないため、DBMにおいても、安全余裕を考慮する必要があります。
また、安全余裕をどの程度の数量とするかは、入荷リードタイムの日数と日々の売上の数量と売上のばらつき具合により、決めることが必要となります。
安全余裕がある場合の発注量の求め方について
DBMにおいては、安全余裕は3分割されるバッファのさらに、下に設定し、上から緑バッファ、黄色バッファ、赤バッファ、安全余裕という4つのゾーンとなります。
また、発注時点での実在庫量がバッファ赤よりも下回り、安全余裕ゾーンの場合は、無条件で、バッファを増やす必要があり、下記のようになります。
- バッファを三等分し、上から緑、黄、赤のゾーンに色分けする。
- バッファの下に、安全余裕のゾーンを置く。
- 発注時点での実在庫量+発注残がどのゾーンにあるかチェックする。
- 安全余裕ゾーンの場合、バッファを増やす。
- バッファ緑またはバッファ赤の場合、連続して何回目かをカウントする。
- バッファ緑の連続回数が規定値に達した場合はバッファを減らす。
- バッファ赤の連続回数が規定値に達した場合はバッファを増やす。
- 実在庫量+発注残がバッファより少ない場合、その差を発注量とする。
安全余裕が多いと、よりバッファ判定がシビアになり、より多くの在庫を持つこととなり、入荷リードタイムが大きい商品の売上のばらつきによる、欠品の防止につながります。
![[図]](images/cons_column01_51_2.gif) 安全余裕と、バッファ判定、発注量の関係
安全余裕と、バッファ判定、発注量の関係
入荷リードタイムが長い場合の問題点について
ここまでに、述べてきたように、入荷リードタイムが長い商品では、発注残や安全余裕の考慮が必要となります。
バッファに対して、安全余裕の割合が大きくなると、バッファの増減による、在庫最適化の効果が出にくくなります。
また、発注時点で発注残があるような商品の場合、実在庫量に発注残を加味して発注量を決める必要があるため、発注担当者の負荷が増えてしまいます。
まとめ
DBMにおいては、入荷リードタイムが長いと、発注残や安全余裕の考慮が必要となり、結果として、在庫最適化の効果が出にくくなります。
できるだけ、入荷リードタイムを短くすることで、在庫最適化の効果が大きくなりますので、DBMの導入の際には、入荷リードタイムの短縮といった業務プロセスの見直しもあわせて実施することが重要と考えます。
- 注:発注してから入荷するまでの日数
執筆
NECネクサソリューションズ
コンサルタント 横澤 雄己
[ITコーディネータ、PMP]