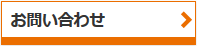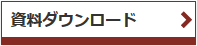コンサルタントのコラム
ビジネスプロセスマネジメント入門
[第4回]ハイレベルビジネスプロセスモデルのレイヤ(層)について
2010年3月(2020年10月改訂)
前回のおさらい:ビジネスプロセスモデルのレイヤとタスクの粒度
前回は、ビジネスプロセスモデルにおけるタスクの粒度についてのお話でした。
その中で、モデリングの目的に合致した粒度までタスクを細分化すること、およびプロセスの粒度の基準を定める(標準化する)ことが大切だと述べて、4つのレイヤを定義しました。
| レイヤ名 | タスクの粒度 | モデルで表現すること | レーン | 他の作成手段 |
|---|---|---|---|---|
| プロセスマップ | End-to-Endプロセスを単位とする粒度 | End-to-Endプロセスの種類と、相関関係 | 設定しない | バリューチェーンタスク一覧表 |
| ハンドオフ | 役割間における責務、情報、物の移転を単位とする粒度 | プロセスの順序、実施条件、同時並行性 | 部門 または 担当 |
(なし) |
| マイルストーン | 業務アサインや、パフォーマンス測定を単位とする粒度 | 同上 | 担当 | (なし) |
| プロシージャ | 担当者の作業を単位とする粒度 | 作業の順序、実施条件、同時並行性 | 担当 | 作業手順書、産能式フローチャート |
今回は、ハンドオフレイヤを中心に、その他のレイヤについても解説します。
プロセスマップレイヤ
「End-to-Endプロセスを単位とする粒度」と定義してみましたが、一般的には全社プロセスおよび、その下の各事業プロセスと考えて良いと思います。
![[図]](images/cons_column02_04.gif) プロセスマップレイヤ
プロセスマップレイヤ
この粒度では、ひとつのタスクに多くの部門や担当者が関連するので、ロール(役割)を表す「スイムレーン」は記述しません。
このレイヤでは、あえてBPMNによるビジネスプロセスモデルを作成する必要はありません。 全社プロセスはバリューチェーンなどで表現されていることが多いので、そのまま利用すれば良いと思います。
ハンドオフレイヤ
ハンドオフレイヤとは「役割間における責務、情報、物の移転を単位とする粒度」ですので、「何かが渡されて作業を開始してから、作業が終了して何かを渡すまで」をひとつのタスクとして表現することが基本となります。
下の図が部門ハンドオフレイヤのビジネスプロセス図の例です。
![[図]](images/cons_column02_04-1.gif) 部門ハンドオフレイヤ
部門ハンドオフレイヤ
ある部門内で行われる一連の仕事を一個のタスクとして表現して、同じレーン(部門)のなかでは連続したタスクを記述しないのが、部門ハンドオフレイヤの原則です。
ただし、例外的にマイルストーンとして着目したいタスクを明示的に記述することもありえます。
![[図]](images/cons_column02_04-2.gif) 部門ハンドオフレイヤでマイルストーンタスクを記述
部門ハンドオフレイヤでマイルストーンタスクを記述
部門ハンドオフレイヤのビジネスプロセスモデルを作成後に、さらに詳細な分析や検討が必要な部分を、担当ハンドオフレイヤとして詳細化します。
![[図]](images/cons_column02_04-3.gif) 担当ハンドオフレイヤ
担当ハンドオフレイヤ
この例では、技術部における担当ハンドオフレイヤが原則どおりに描かれています。
「技術部が見積依頼を受けてから承認済みの見積ができあがるまで」が、パフォーマンスを把握したいプロセスならば、「見積依頼受付」と「見積完了登録」がマイルストーンタスクとなりますので、このビジネスプロセスモデルは「マイルストーンレイヤ」であるとも言えます。
プロシージャレイヤ
「担当者の作業を単位とする粒度」という、最も小さい粒度のビジネスプロセスモデルです。
ある担当者の業務パフォーマンスが、上位のプロセスのパフォーマンスに大きな影響を与えると判断された場合に限りプロシージャレイヤのモデルを作成するように心がけるべきです。
多くの場合、前述の担当ハンドオフレイヤにマイルストーンタスクを明示することで、プロシージャレイヤの粒度のモデリングを省略することができます。
![[図]](images/cons_column02_04-4.gif) プロシージャレイヤ
プロシージャレイヤ
この粒度のモデルでは、利用されるITシステムを機能単位に表現できるため、ハイレベルモデルをITシステム要求定義の検討に利用する場合には、プロシージャレイヤのビジネスプロセスモデルが、たくさん作成されることがあります。
必要な業務のみモデリングする
前回お話したことの繰り返しになりますが、すべての業務をプロシージャレイヤの粒度で描くことは、ハイレベルモデルの目的から考えて、あまり意味のない作業です。
まずは部門ハンドオフの粒度で業務一覧を作成し、必要な業務のビジネスプロセスをモデリングし、どうしても必要な業務に関してのみ、より小さい粒度のプロセスを描くことを心がけてください。
執筆
NECネクサソリューションズ
シニアコンサルタント 冨澤 雅彦
[日本TOC推進協議会 正会員、日本UML推進協議会 BPMN研究会副主査]
本コラムに関連するコンサルティングサービス
- ITシステム企画サービス
ツボを押さえたシステム企画を立案し、次期ITシステムの投資対効果を最大化します。