刈谷 優孝(かりや まさたか)氏
株式会社日本能率協会コンサルティング
生産コンサルティング事業本部
チーフ・コンサルタント
- 物流業(荷主/物流事業者)、製造業を中心にサプライチェーンやロジスティクス全体の改革構想の立案、物流・製造現場の生産性向上、情報システムの構築など幅広いテーマに知見をもつ。
- BtoC業界においては主に食品小売や医療機器などの業界でマテハン導入,3PL選定,物流システム導入,LOM設計など含めた新物流センター建設プロジェクト、BtoB業界では建材、工作機械などの業界で物流ネットワーク再編プロジェクトなど複数テーマを経験している。

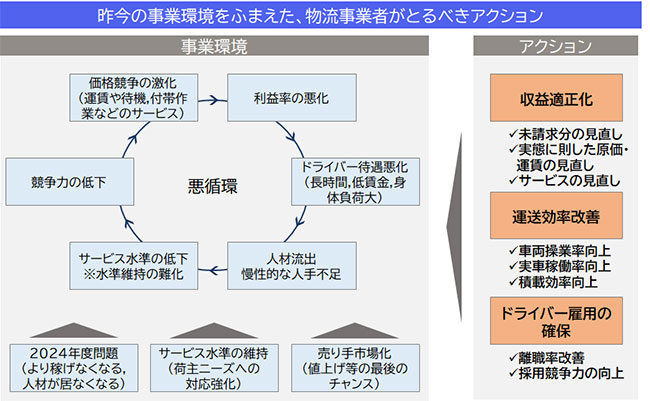
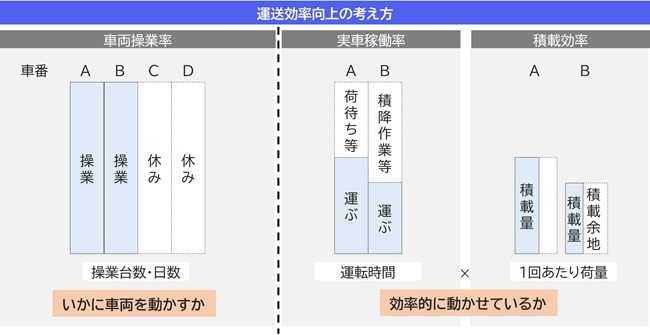
 製造業・プロセス型製造業向けコラム
製造業・プロセス型製造業向けコラム