石﨑 勇人 (いしざき ゆうと)氏
株式会社日本能率協会コンサルティング
生産コンサルティング事業本部
サプライチェーン・デザイン&マネジメントユニット コンサルタント
工作機械メーカーにて生産管理領域の業務に従事し、生産計画の立案や進捗管理、新製品立ち上げ業務に関わった後、 株式会社日本能率協会コンサルティングに入社。
生産管理領域の知見を活かし、製造現場に入り込み、計画立案~実行まで一貫した支援を強みとしている。
近年では物流領域や製造現場の生産性向上など、製造業に関連する幅広いテーマでのコンサルティングを行っている。
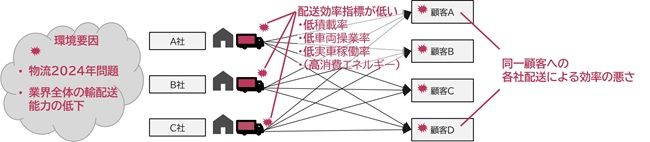
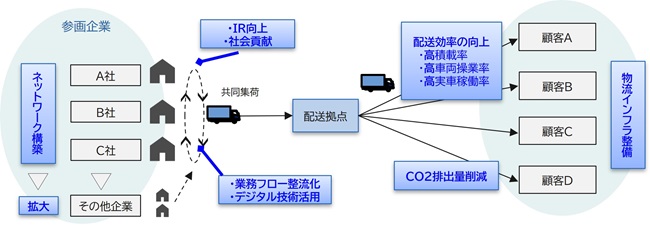

 製造業・プロセス型製造業向けコラム
製造業・プロセス型製造業向けコラム