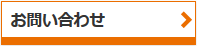公認会計士が回答!会計・経理担当者向けペーパーレスへの取り組み(第4回)
すぐにゴールを目指さない段階的な電子化も検討を
2022年11月
Q.
書類の電子化を考える場合、受領した書類をスキャナで読み込んで電子化するより、そもそも書類に記載されるべき情報を電子データで取得する電子取引の方が好ましいと思っています。しかし、多くの取引先との折衝に手間がかかりそうで困っています。
A.
(1)目指すべきゴールは電子取引だが
DXや電子化を考える場合、単に紙の書類を電子的に保存するのではなく、電子データを利用して、業務の自動化を図っていくのが本来のデジタル化です。納品書と請求明細書を照合して、請求書の内容がすべて納品されているかどうかを確かめるといった処理を行うのであれば、電子取引によって納品書データ、請求明細データを取得できるのが理想です。
スキャナ保存でも電子化はできますが、本連載の第3回でも触れたように電子化の後にOCR処理を行い、さらに客先側の商品コードを自社の商品コードに置き換えるといった手順を入れなければいけないのは手間だと感じられるはずです。だからといって、「何が何でも電子取引に移行しなければ」と力んでみても、電子取引は取引先にも対応してもらえない限り実現はできません。
(2)スキャナ保存から電子取引へと段階的な電子化を
そこで考えてみたいのが、まずはスキャナ保存を導入し、これを利用している間に取引先との電子取引への話し合いを進めるという段階的な電子化です。スキャナ保存は、自社の意思決定で直ちに導入を決定できる手法です。そこで、まずはスキャナ保存を実施して、電子化されたデータを利用して、照合の自動化の実現へとシステムを構築します。そして、ここから5年といったスパンで考えれば、DXは一層浸透しているはずで、5年の間に取引先との交渉を進めていくことで、5年後には電子取引を実施しようという長期計画を持ってみてはいかがでしょうか。
スキャナ保存のシステムの耐用年数を考えると5~6年です。そして、電子化されたデータを用いた照合の自動化システムの部分は、プログラムなので電子取引に移行してからも利用することができます。電子取引に向けての取引先との交渉の間、紙の書面を相手に手作業を続けるのではなく、まずはスキャナ保存を導入するのです。そして、会社内の従業員に電子化された業務環境に慣れてもらい、電子取引の段階にも活用できる自動化システムを作り上げます。
5年後に電子取引に移行できるという段階に至った時には、スキャナ保存システムは税務上および実務上の耐用年数を迎える頃ですから、スキャナ保存システムに対する初期投資は、電子化による生産性向上で回収できていると考えることができます。しかも、照合の自動化の部分のルーチンは、電子取引でも生かせますので、電子取引になってもデータの入口の部分が変わるだけで、大きな変更がないため、スムーズな移行が期待できます。
書面が電子ファイルになることで、そのデータへのアクセス権を与えられた従業員は書類の保管場所へ行かなくてもデータを見ることができるようになります。そのため、従来は本店、支店、工場など部署ごとに書類のコピーやPDF化をしていたかもしれず、その手間や紙代、トナー代の節減も図れます。
スキャナ保存から始まる段階的な電子化計画を考えてみてはいかがでしょうか。
取引先からの紙書類の取扱いを効率化しませんか?
社内のデジタル化が進み、ペーパーレスによる業務改善が進んでも、取引先から届く注文書や請求書のような紙の書類は、まだまだ残っているのではないでしょうか?
自社だけの力ではどうしようもない取引先からの紙の書類の取扱いや基幹システムへの登録までの業務全体を、デジタル化・ペーパーレス化することで、業務効率をあげリードタイム短縮を考えてみませんか?