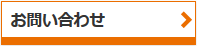公認会計士が回答!会計・経理担当者向けペーパーレスへの取り組み(第9回)
電子契約と情報セキュリティについて考える
2023年4月
Q.
当社では、取引電子化の一環として、電子契約への移行を積極的に進めようとしています。そのなかで、契約内容によっては、たとえば、商業登記、不動産登記などで電子契約書が使えるのかといった各種法律での電子契約書の取扱いの状況、あるいは電子契約による契約書の法律的な効果は書面と同じなのかといった疑問があります。電子契約の効力と安全性について教えてください。
A.
(1)契約書の真正性とはなんだろう
契約とは、法的な約束ごとであり、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示と、それに対する承諾により成立します(民法522条1項)。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないとされています(民法522条2項)。すなわち、口頭でも契約は成立するわけですが、口頭での契約では後で「そんな約束をした覚えはない」とか「私ではない誰かが勝手に約束したのだろう」など契約を覆すことが容易であり、法律的に不安定になってしまいます。そのため、書面で契約内容を記述し、契約当事者が実印で捺印をして、印鑑証明書を交換すれば安全な契約書になると言われています。実印は、一般的に本人だけが持ち歩くものであり、印鑑証明書も厳格な本人確認を経て印鑑登録されたうえでの証明です。実印で捺印して印鑑証明書まで交付しておいて、「押したのは自分ではない」とは言えないことになります。また、契約書の勝手な書き換えはできませんから、内容の真実性、なりすまし防止、自己否認の防止など真正性が確保されるわけです。
(2)電子契約と情報セキュリティ
一般に情報セキュリティとして、機密性(confidentiality)、完全性(integrity)、 可用性(availability)、真正性(Authenticity)、信頼性(Reliability)、責任追跡性(Accountability)、否認防止(non-repudiation)の7つが挙げられることがあります。書面の契約書であげた内容の真実性、なりすまし防止、自己否認の防止は、完全性、真正性、否認防止といった内容です。また、会社の契約が誰からでも見えてしまったら困る(機密性)わけで、紙のうえでの安全性の確保を情報技術の活用によりデジタル上でも実現することができるようになってきたために電子契約が活用されるようになってきているのだと考えることができます。
書面の契約でも日頃から取引のある相手から送られた「品番××を△個発注します」といった電子メールであれば、あまり情報セキュリティを考えずに「了解です。納期は〇日です」といった返事のメールで契約成立となります。しかし、ご質問のように不動産売買などの契約では、地面師といった言葉があるように詐欺的な行為も存在するわけで、登記の実務上は、きわめて厳格な情報セキュリティが求められます。2022年5月18日より、定期借家権の契約その他で電子契約(電磁的記録による締結)が認められるようになってきました。しかし、商業登記電子署名や個人のマイナンバーカードの電子署名が必要です。やはり、印鑑証明書に代わる情報セキュリティとなると、会社や個人について厳重な認証手続を経た電子署名が必要だということなのでしょう。
逆に、民間の電子契約サービス提供会社の電子契約は、実印及び印鑑証明書並みの究極の情報セキュリティではないことになります。たとえば、電子契約の際に利用される、受信者のメールアドレス宛に契約締結のためのサイトへのユニークなURLが送られることでの本人確認システムは、本当に代表権を持った本人のメールアドレスを代表者本人が読み書きしているという保証があってこその認証方法です。ただし、日頃から様々な事項をやり取りしてきているメールアドレスの間では、一定期間の中で、対面や電話でもメールの内容にも触れたやり取りをしているわけで、必ずしも代表者ではなくても発注権限のある人であるといった信頼性が形成されています。こうした関係性の中では、電子契約は十分に機能します。反対に、ネット上で初めて会う人同士の契約で電子契約が使えるかというと不安が残るのではないでしょうか。
したがって、ファックスや三文判や角印といった信頼性よりは堅固だが、印鑑証明書付きの実印による契約には至らないといった程度の認識で電子契約書を理解することになるでしょうか。あるいは一定の信頼関係が形成された関係者間での契約のツールであると考えても良いでしょう。それでも電子契約は十分に便利な取引ツールだと考えられます。また、通常の利用局面を想定するならば、裁判上は証拠として十分に機能すると考えてよいことになります。
情報セキュリティの概念について正しい理解を持ちつつ、従来の書面での安全性確保の仕組みと対比をしながら、新しいツールを理解するならば、電子契約など新しい情報ツールを活用することでペーパーレス、情報共有を可能として、テレワークも容易になるなど、大きなメリットを得ることができるのではないでしょうか。