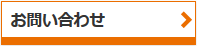公認会計士が回答!会計・経理担当者向けペーパーレスへの取り組み(第11回)
部門ごとに使用しているソフトが違うことで生まれる課題とは
2023年7月
Q.
当社は、従業員200名ほどの企業ですが、各部門の判断でパッケージソフトを導入してきました。そのため、人事部の給与ソフトと経理部の会計ソフトのメーカーが異なり、給与仕訳は手入力です。また、販売管理システムと購買管理システムと会計ソフトも異なるメーカーの製品を使用しているため、定型的な仕訳伝票入力が繰り返し大量に発生しています。また各システムと会計ソフトで二重入力を行っていることになり、作業量が多く経理部門の残業も減らない状況です。そうした中で、各システムと会計ソフトが連携できれば入力作業が大幅に削減され、またデータが紐付けされることで今後の電子取引の保存義務やインボイス制度対応にも有効ではないかと考えています。どのような方策があるのでしょうか。
A.
(1)システムの導入の方針
システムの導入や運用に際しては、一定規模以上の会社であれば、システム部門が存在し、その中で全社的なシステム戦略を構築し、その戦略に沿った形で個々のシステムの導入が実施されていきます。相談者の会社の場合、システム部門を置くほどの規模ではなかった、もしくはトップダウンでのシステム戦略が検討されてこなかったなどの理由により、各部署が必要に迫られてパッケージソフトを導入していったのではないでしょうか。逆にもう少し規模の小さい企業であれば、「経理には××会計が入っているから、総務・人事でシステムを入れるなら××会計と連携できるものにした方がよいだろう」といったことを経理のすぐ隣の総務部門は考えるはずです。
また、多くの企業では、販売管理システムや購買管理システムと会計システムの連携という発想は従来なかったと思われます。納品書や請求書の発行を手書きでやっているわけにはいかないから、在庫管理をするうえでも受払いをシステムで管理せざるをえないといったニーズからシステム導入するわけで、会計システムと連携の必要性は現場部門にはありません。そのため、販売管理システムで把握している売掛金残高と会計システムの売掛金残高に不一致が生じているような事態が生じることもあります。
相談者の会社においては、ここで電子帳簿保存法改正の流れの中で、経費精算システムや電子ファイル管理システムを社内の連携を考えることなしに導入するのは、さらにシステムの関連性を複雑にしてしまうものと思われます。これらのシステムは、会計システムとの連携を重視したもの、ワークフローなど社内の承認プロセスの一環としてのシステムなど特色があります。各システムとの連携を検討せずに導入すると、経費精算でも会計仕訳を手入力しなければいけない、あるいは承認プロセスの設定の柔軟性がないなどの不満が残ることになります。
(2)ERPという選択肢
こうした状況では、思い切って社内のシステムの多くを刷新することとして、ERPシステムを導入するというのは解決策の1つとなります。ERPとは、Enterprise Resource Planning(企業資源計画)の略ですが、日本では、基幹システム、業務統合パッケージといった呼び方をすることもあります。ERPは、企業の「会計業務」「人事業務」「生産業務」「物流業務」「販売業務」などの基幹となる業務を統合し、効率化、情報の一元化を図るためのシステムとして誕生しました。商品を仕入れれば、在庫が増え、その在庫を販売すれば、売上高が計上され、その結果は、仕入高、売上原価、売上高といったかたちで会計システムに取り込まれるわけで、そうした業務を統合的に行えるように作られたパッケージシステムとなっています。従来、会計システムとして出発したシステム会社も販売管理システムや購買管理システムを発売して、それぞれのデータの連携をすることでERPシステムと称するようになっています。しかし、本来は、経営データの統合管理と経営情報の見える化を実現することが企業のリソースの最適化の計画につながるわけで、Enterprise Resource Planning という言葉を実現するようにデータの一元管理を前提に開発されたものが本来のERPであるといえます。インボイス制度への対応を考えても、インボイスの発行や受領は業務部門であり、それらの結果としての消費税計算は経理部門です。それぞれの部門のシステムが有機的に連携した一元管理になっていれば、インボイス対応もスムーズになるはずです。
(3)利用部門を巻き込んだシステム導入を
近年、ERPシステムは、超大企業が利用するようなものだけでなく、中堅企業、中小企業でも導入できるようなものが様々なシステム会社から発売されるに至っています。そうしたシステムの中から、自社に適したシステムを選定し、計画的に導入していくことが必要です。
その中で重要なことは、自社の今後の成長を考えるうえで、社内に分散しているデータを統合管理する必要性を各部門に訴え、そのうえで、各部門からシステム選定のためにも、各部門が現在のシステムをどのように使っていて、実現できていないが欲しい機能などを持ち寄ってもらい、システム選定のための情報を集めることが必要です。こうしたことをスタートする上でも、トップダウンでのプロジェクトなのだという権威と権限を付与し、各部門から部門内の業務の流れを把握している優秀な人材にプロジェクトメンバーとして集まってもらうことが必要でしょう。
このように書くと、非常に障壁が高くなるようにも思われるかもしれません。しかしながら、おそらくこのプロジェクトメンバーが10年後、20年後の自社の幹部社員になる可能性が高いわけで、会社全体を見渡すという視点を身につけてもらうためにもこうしたプロジェクトを実施することには価値があると思われます。