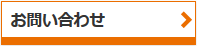公認会計士が回答!会計・経理担当者向けペーパーレスへの取り組み(第5回)
電子取引データだけではない保存すべき対象物
2022年12月
Q.
当社では、EDI取引を利用して、購買取引業務を行っています。発注データの送信、納品書データ、請求明細データの受信などを行い、購買管理システムと在庫管理システムで仕入商品の管理を行っています。電子取引データの保存のサブシステムを開発中ですが、これに関して留意すべき事項はありますか?
A.
(1)電子取引の取引情報の保存
令和3年税制改正により電子取引の取引情報の保存が義務付けられました。以前は、書面で出力していれば、電子保存に代えることができるという取り扱いがありましたが、この取り扱いが消滅し、実務界には大きなインパクトがありました。そのため、令和5年12月31日までの宥恕期間が設けられたことはみなさまご承知のとおりです。これまで購買管理や販売管理にEDI取引を利用していた会社で、その取引情報データの電子保存ができていなかった会社では、データ保存ができるようなシステム改修をする必要が生じ、これを宥恕期間の間に完了させる必要があるということになります。
電子取引の保存にあたっては、(1)システム開発関係書類の保存、(2)見読可能性の確保、(3)検索性の確保、(4)真実性の確保が必要です。真実性の確保にあたっては、やり取りする取引情報データにタイムスタンプを付してから送受信することや、訂正・削除の履歴が残るようなシステムであることなど、4通りの方法の中で保存データの真実性を確保する必要があります。こうした保存要件を充足する形でのシステム改修が必要です。
(2)関連する補助簿の出力・保存はできているか
法人税法施行規則第54条では、青色申告法人は、仕訳帳、総勘定元帳その他必要な帳簿を備えて、取引に関する事項を記載しなければならないと定められています。たとえば、商品在庫受払帳、商品出納帳といった帳簿で仕入れた商品の受払いに関する取引が記載される必要がありますし、販売に関しては売上帳、得意先元帳など、仕入に関しては仕入先元帳、買掛金元帳といった帳簿が作成されなければいけないことになります。仕訳帳、総勘定元帳を主要簿というのに対して、その他の帳簿は、補助簿と言われます。
帳簿というと経理部門の担当というイメージがありますが、商品に関するデータは購買管理システムや在庫管理システムに保管されています。経理部門が所管する会計システムに必要なデータが送られていない限り、上述したような商品出納帳などの補助簿は、会計システムからでは出力できません。なぜなら商品1品ごとに、いつ、どの仕入先からいくらで何個仕入れたかというデータと、いつ、何個払い出したというデータがなければ商品出納帳は作成できません。購買管理システムから当月の仕入先ごとの合計仕入金額のデータだけを会計システムに受け渡している場合、当然ながら、会計システムから商品出納帳を作成することはできません。
こうした場合、仕入や商品に関する補助簿の出力は、購買管理システムや在庫管理システムから行わざるを得ません。これらを書面で出力するとかなりの分量になるため、これまで出力をしてこなかったかもしれません。きちんと出力してきたのであれば、これを電子保存するということも令和3年度の改正で容易になっています。また、こうした必要性自体を認識していなかったため、出力はしてこなかったという場合には、電子保存でよいので、電子帳簿保存法の要件を満たしながら電子保存するようにしなければなりません。
これまで補助簿の出力の必要性など問われたことがなかったというのが購買取引業務の担当部署の実感かもしれません。おそらく過去のシステム化の過程で、経理部門とのやり取りが十分でなく、補助簿を作成するということがシステム開発計画の中に織り込まれなかったこともあるはずです。要件定義から漏れていたということになります。過去の経緯はともかく、結果として法人税法の求める状況になっていないというのは、コンプライアンス(法令遵守、社会規範性)の観点でも問題なので、この機会にシステム改修をしておきたいものです。
取引先からの紙書類の取扱いを効率化しませんか?
社内のデジタル化が進み、ペーパーレスによる業務改善が進んでも、取引先から届く注文書や請求書のような紙の書類は、まだまだ残っているのではないでしょうか?
自社だけの力ではどうしようもない取引先からの紙の書類の取扱いや基幹システムへの登録までの業務全体を、デジタル化・ペーパーレス化することで、業務効率をあげリードタイム短縮を考えてみませんか?