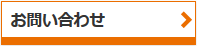公認会計士が回答!会計・経理担当者向けペーパーレスへの取り組み(第7回)
令和5年度税制改正で電子取引の保存は緩和になったのか
2023年2月
Q.
当社では、ダウンロードされた出張時の航空券予約代金の領収書や、電子メールに添付されてくるPDFファイルの領収書などの電子取引について、必ずしも大量ではないため、書面に出力したうえで経理処理・保存するという業務の流れを変えたくありません。令和5年度税制改正で電子取引の保存要件の緩和があったと聞きましたが、どのような改正なのでしょうか。
A.
(1)電子取引に関する令和5年度税制改正
令和3年度税制改正で電子取引の保存義務が打ち出されましたが、電子取引の概念は、いわゆる電子商取引など特定の取引先との大量のデータのやり取りのための電子取引ばかりでなく、ネット通販やホテルのネット予約のほか請求書のPDFファイルを電子メールに添付してやり取りするような行為も対象に入っていたため、中小企業も含めて、多大な影響が生じることになりました。このため、令和4年度税制改正で2年間の宥恕(ゆうじょ)期間が設けられることになり、実質的には令和5年12月いっぱいは、従来通りの処理、すなわち電子取引による取引情報を書面に出力して、保存することができることになりました。
しかし、電子商取引のシステムは、販売や仕入れなど経理側より製造、販売、購買といった部門で利用されることが多く、電子取引の取引情報の保存や、それに代わる書面での取引情報の出力という発想自体が弱かったため、2年程度の宥恕期間では十分なシステム改修の時間がありませんでした。また、ネット通販やホテルのネット予約などの電子取引は、零細企業でも利用されていたため、電子取引情報を管理する証憑管理システムを導入したのではコストの増加に耐えられない企業も多く存在していました。宥恕期間を置くという発想は、すべての企業が電子保存できる状況に向かって対処する前提でしたので、コスト的に見合わないという企業の存在は想定していなかったのかもしれません。
そのため、令和5年度税制改正大綱では、保存要件の緩和と保存が困難な企業への対処という2つの措置が講じられました。
(2)保存要件の緩和
保存義務者が税務職員の質問検査権に基づく電磁的記録の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、下記の場合に検索要件のすべてを不要とする措置について、対象者を次のように定めました。
| 要件 | 令和3年度改正 | 令和5年度改正 |
|---|---|---|
| 検索要件のすべてを不要とする対象者 | 売上高1000万円以下である保存義務者 | 売上高5000万円以下である保存義務者 |
| 電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者 | - | 整然とした形式及び明瞭な状態、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された出力書面があれば可 |
従来、売上高1000万円以下という極めて小規模の事業者にしか検索要件不要という措置は適用されていませんでしたが、売上高5000万円まで拡大されたことで、電子ファイル保存システムなどを導入してもコスト倒れになる規模の事業者への配慮が進んだことになります。また、この基準は、消費税の簡易課税が適用される課税売上高5000万円の基準とも近いことで、みなし仕入れ税額控除により課税仕入に係る請求書等の保存の必要がなかった事業者への配慮がされたと考えることもできるでしょう。
そして、もう1つ整然とした形式及び明瞭な状態、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された出力書面があれば、電磁的記録は、提示、提出できるようにしておくだけで検索性は不要という枠組みも誕生しました。質問者の会社では、新たに電磁的記録の保存もしておく必要はあるものの、従来の業務の流れは変えることなく、電子取引に対応することができることになりました。
また、上記と別に電磁的記録の保存を行う者に関する情報の確認要件を廃止するとされましたので、タイムスタンプを付すような場合に緩和がされたことになります。
(3)保存が困難な企業への対処
納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、質問検査権に基づく当該電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件に関わらず、その電磁的記録の保存をすることができることとされました。
「相当の理由」としてどのようなものが例示されるのかによって、使い勝手の良し悪しはまったく違ってしまうことになります。例えば、電子商取引システムにおいて、そのシステムが取引相手側の開発したもので、その使用を求められて電子取引を行っていたにも関わらず、その取引相手が電子保存を可能にするバージョンアップをしてくれていないといった場合などは、文句なしに「相当の理由」になりそうに思えます。自らが開発したわけではないシステムの改修は、通常は極めて困難であるからです。そのほかにどのような相当な理由の例示が出てくるのかは、本年6月頃の取扱通達や一問一答の改正を待つことになるでしょう。
(4)企業規模による対処の違い
(2)の保存要件の緩和で説明したように電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者が、整然とした形式及び明瞭な状態、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された出力書面を提出、提示できるようにしていれば、企業規模に関わらず検索性の要件は考えずに電子取引の取引記録の電磁的記録を保存することができることになりました。ということは、旅費精算・経費精算において従来通り、電子取引で入手したPDFファイルなどを出力したうえで精算書に添付するような実務を変える必要性がないことになりました。ただし、電磁的記録の保存も必要ですので、真実性確保のための要件、パソコンなど見読可能性の確保の要件などに配慮してデータ自体は保存する必要があります。
ここで検索性の確保が電子帳簿保存法として求められていないというのは助かりますが、会社の経理事務として本来の原本である電子データへのリンクが不明瞭なのは困ります。年間、数百枚を超えるようなデータ件数になってくるようであれば、比較的簡易なシステムでもよいので、電子ファイル管理システムを導入するということも考えてみるべきだと思われます。
改正電帳法対応から業務のデジタル化を始めませんか
- 人手を介在させる領域をシステム化で減らすことが可能
- 進捗状況を可視化し、管理者・作業者共にやるべきことがわかりやすくなる
- 情報の転送・加工をシステムが実行。自動化も可能
電帳法の対応と併せてアナログ業務のデジタル化を進めることによって下記のようなメリットが生まれます。
運用イメージやシステム例なども併せてご紹介します。