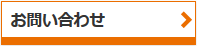公認会計士が回答!会計・経理担当者向けペーパーレスへの取り組み(第10回)
電子商取引システムでの令和5年度税制改正対応
2023年6月
Q.
当社では、自社開発した電子商取引システムで部材の仕入先への発注や納品書・請求書の受領などを電子取引により行っています。しかし、電子帳簿保存法への対処など想定もしていない時期にシステムの開発をしており、また、これまで税務調査等で電子商取引システムに触れられたことがなかったため、取引データの長期保存ができない仕様です。上司からは、「書面に出力して、整理保存しておけばよいことになったのだから、このままでよいのではないか」と言われ困っています。
A.
(1)電子取引の2つの類型
令和3年度税制改正での電子取引の保存義務化から注目をされている電子取引ですが、筆者は二つの類型に区分して理解するのがよいと考えています。
| 典型的な電子取引 | いわゆるEDIなど、特定の取引について定型的かつ大量のデータのやり取りを行う電子取引 |
|---|---|
| 単発的・非定型的な電子取引 | メールに添付されたPDFファイルや買い物後にWebサイトから領収書をダウンロードするなどの多くの従業員が単発的・非定型的に行う電子取引 |
ご質問の電子商取引システムは、メーカーにおける部材仕入れという大量のデータのやり取りを行うシステムとなっているはずで、上記の類型では、典型的な電子取引に該当することになるはずです。この場合、やり取りするデータの量が大量であり、これまでも注文書控え、注文請書、納品書、請求明細書、請求書に相当する取引情報を受領してきても、書面での出力などしてこなかったと思われます。これは、改正前の電子帳簿保存法への理解がなかったこともありますが、大量であり、かつ日々の業務が順調に進んでいれば、ほとんど見ることもない資料を書面出力するのは無駄だったからだと思います。
税務調査でも触れられたことがなかったということですが、そもそも本件のような電子商取引システムは、工場など現業部門に設置されており、本社の経理部門で行われる税務調査では触れられにくいところにあったため、ITに詳しい税務調査官に当たらない限り、そうした現業部門のシステムにまで調査対象とすることが困難だったのが理由だと思われます。決して、税務調査の対象外だったということではありません。電子帳簿保存法の改正により、今後は、電子取引の取引情報の電磁的記録の保存状況を見てみようという意識が税務調査官の中でも高まってくる可能性があります。
(2)電子取引に関する令和5年度税制改正
この連載の第7回でも触れた電子取引に関する令和5年度改正ですが、次のような二つの改正により、電子取引の規模が小さい企業への配慮がされることになりました。保存義務者が税務職員の質問検査権に基づく電磁的記録の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、下記の場合に検索要件のすべてを不要とする措置について、対象者を次のように定めました。
| 要件 | 令和3年度改正 | 令和5年度改正 |
|---|---|---|
| 検索要件のすべてを不要とする対象者 | 売上高1000万円以下である保存義務者 | 売上高5000万円以下である保存義務者 |
| 電磁的記録の出力書面の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている保存義務者 | - | 整然とした形式及び明瞭な状態、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された出力書面があれば可 |
質問者の上司は、おそらく上記の二つ目、「整然とした形式及び明瞭な状態、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された出力書面」を用意しておくことで済むと考えたのだと思いますが、それは適切ではありません。というのは、この緩和策は、あくまで電子データの方も保存自体は必要であるとされていて、検索要件のすべてを不要とする措置として導入されたものに過ぎません。現状のシステムで長期保存ができない以上、そもそも電子帳簿保存法違反の状況から逃れることはできません。上記の検索要件を不要とする措置は、主として前述(1)で掲げた「単発的・非定型的な電子取引」の類型の電子取引への取扱いだと理解するべきです。
(3)令和5年12月末までにシステム改修を
現在は、令和4年1月から2年間の宥恕期間にありますので、書面の出力があれば、電子データ自体の保存は不要です。したがって、システム改修は、令和5年12月末までに終えて、令和6年1月からは、電磁的記録の保存をスタートしなければなりません。今から、改修のための発注をして間に合うかどうか難しいところかもしれません。
今般の令和5年度税制改正では、もう一つ電磁的記録の保存が困難である企業への対処が盛り込まれています。それは、納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存することができなかったことについて相当の理由があると認め、かつ、質問検査権に基づく当該電磁的記録のダウンロードの求め及び当該電磁的記録の出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る。)の提示又は提出の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件に関わらず、その電磁的記録の保存をすることができるという取扱いです。
すなわち、「保存ができなかったことへの相当の理由」があれば、検索性だけでなく、真実性確保などの要件も満たさない状態で、とりあえず電磁的記録が保存されていればよいという意味合いです。この場合、たとえば、電子商取引の取引データをcsvファイルやPDFファイルに出力して、一応、見ることはできるといったことでも許されるということになります。しかし、この取扱いは、電子帳簿保存法施行規則の中で、災害等で電磁的記録を保存できなかった場合などと同じ条文で定められており、適用できるのは極めてまれな場合ではないかと予想されます。「相当の理由」の例示は、本年6月ないし7月の通達の改正などによって明らかになると思われますが、システム改修の発注をしているが、その納品時期が令和6年にずれ込んでしまったといったような場合などは、例示に入ってくるかもしれません。逆に言えば、それくらいに厳しいのだと想定して、今から保存機能の仕様追加の検討をスタートすべきでしょう。