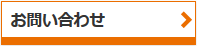公認会計士が回答!会計・経理担当者向けペーパーレスへの取り組み(第6回)
保存すべき電子データとはなにか
2023年1月
Q.
当社では、EDI取引を利用して、購買取引業務を行っています。発注データの送信、納品書データ、請求明細データの受信などにあたっては、各データは暗号化したうえで送受信しています。電子取引の取引情報の保存義務を文字通りに解せば、暗号化したデータを保存することになるのですが、これでは内容を見ることができませんが、良いのでしょうか。
A.
(1)暗号化データによる電子取引の場合
電子取引の取引情報に係る電磁的記録は、ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で出力されることが必要です。国税庁が出した取扱通達によれば、暗号化されたデータそのものではなく、受信情報にあってはトランスレータによる変換後、送信情報にあっては変換前のデータを保存することが必要だとされています。もちろん、暗号化されたデータを保存データとしつつも、取引データの閲覧をする際にデータを復号・変換したうえで、取引情報として閲覧可能としたり、検索の対象とするといったシステムになっていれば、それでもかまいません。しかし、暗号化されたデータを復号・変換するだけであれば、その内容を変更したり、追加・削除するような行為ではないと考え、このような通達の内容となっているものと考えられます。
(2)データの取扱いに関するその他の留意点
そのほか、取扱通達の中では、取引情報に係る電磁的記録は、あらかじめ授受されている単価等のマスター情報を含んで出力されることを要するといった定めもあります。これは、通常のEDI取引では、商品の発注データであれば、発注日、商品コード、数量その他の限定された情報がやり取りされますが、取引情報を閲覧する画面では、商品マスターや価格マスターも参照したうえで、商品名や発注金額などもわかるようにしてほしいという意味合いです。
このように税務において求められるのは、データの記載内容が変わっては困るものの、求めるものはデータを視認できるようにできることです。そのため、EDI取引のシステムにデータの検索や長期保存の仕様を追加するのが困難であれば、取引データを出力して、帳票閲覧システムで保存し、閲覧に供するということも可能だとされています。また、EDI取引においてデータをXML形式でやり取りしている場合であって、当該XML形式のデータを一覧表としてエクセル形式に変換して保存するときは、その過程において取引内容が変更されていない限りは、合理的な方法により編集したものと考えられるため、当該エクセル形式のデータによる保存も認められるといった例示もされています。
半面、授受したデータを手動により転記して別形式のデータを作成する場合は、取引内容の変更可能性があることから、当該別形式のデータは合理的に編集したものに当たらないものと考えられるといった注意もされています。手作業でのデータ編集作業があれば、過失によりデータの内容が書き換えられてしまう可能性もあるわけで、当然の要請だと言えるでしょう。そのため、受領したデータのうち、商品コードについては、取引先側の商品コードを自社仕様の商品コードに変換したうえで、電子取引データの保存とすることも認められるわけですが、変換テーブルなどを用いて、自動変換する必要があるということになります。
データ形式やメディアを意識せず社内に散在する情報を一元管理しませんか?
- 文書が社内に分散して保管されているので、必要な書類を捜すのが大変
- 文書の管理方法が部署ごと、個人任せになっている
- どれが最新の文書かわからない
このような課題を文書管理システム「QuickBinder(クイックバインダー)」が解決します。