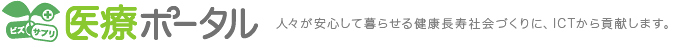
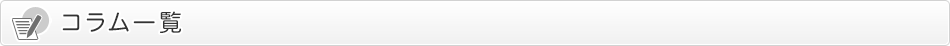


前回は、看護師の主な離職理由の中で、「ライフイベントに伴う離職が多いこと」や「スキルアップ・キャリアアップのための離職が多いこと」に触れたが、今回は、手当や福利厚生面から離職率の高い看護師をいかに定着させるべきかについて記載する。... 続きを読む
前回は、看護師の負担軽減を実現するためには、他の職種の理解が必要であること及び看護補助者の配置の有無が大きく影響すること等に触れたが、今回は、離職率の高い看護師をいかに定着させるべきかについて記載する。... 続きを読む


A病院では、令和4年度の中途からではあったが、勤怠管理システムを導入することを決め、病院勤務医には、ビーコン打刻が最もマッチすると判断された。その結果に戻づいて、最終的に絞り込んだ2社のシステムの比較と勤怠管理システム導入後の問題点等について記述したい。... 続きを読む
医師のみならず医療従事者全員においても「働き方改革」が求められている現状がある。現在、各医療機関においても様々な取り組みが検討されていると思われるが、今回は、A病院における働き方改革の一環として、「勤怠管理システム」の必要性について取り組んだ事例をご紹介したい。... 続きを読む

~医療DX推進に関する工程表(案)から読み解く
後編「医療DX推進により実現に向けた具体的施策と到達点」について~
前回は前編として2023年6月2日に内閣府医療DX推進本部より示された「医療DX推進に関する工程表(案)」より「医療DX推進により実現を目指す5項目」について整備内容や時期について書かせていただいた。... 続きを読む
~医療DX推進に関する工程表(案)から読み解く
前編「医療DX推進により実現を目指す5項目・整備内容と時期」について~
以前も医療DXについて書かせていただいた。その際、医療DX推進の背景として「2025年問題」があると書かせていただいた。その2025年が目前となる中、医療DXとしては次のステージとなる「ポスト2025年問題」への対応として医療DX推進に関する工程がテーマとなり検討が進められた。... 続きを読む

2024年4月より適用される「医師の働き方改革」について考える
~施行前に内容を理解し取り組むべきこととは~
2024年4月より適用される「医師の働き方改革」、今回はこちらについて書かせていただきたい。まず、働き方改自体は2017年3月に施行され、一般企業では大企業が2019年4月、中小企業は2020年4月に既に適用されている。医療など、労働時間が長い分野に関しては現在適用が猶予されている状況であり、いよいよ2024年4月からの適用となる。... 続きを読む

病院は空港と同等の快適さとコストカットを実現できるか〜病院におけるDX推進〜【第3回】
本コラムでは、病院におけるDX(Digital Transformation)について紹介しています。第3部となる今回は、DXによるサービス向上とコストカットの両立についてお話しします。... 続きを読む
あと払い決済のニーズ急増の理由〜病院におけるDX推進〜【第2回】
医療機関におけるDXが注目される中、現在特に病院からニーズが高まっているのが「医療費のあと払い決済」。弊社でも病院向けのあと払い決済システムを取り扱っていますが、全国の様々な施設規模の病院から問い合わせが来ています。今回のコラムでは、「あと払い決済のニーズ急増の理由」を、実際に弊社に問い合わせのあった病院から収集した意見をもとに紹介します。... 続きを読む
診察の待ち時間をどうするか〜病院におけるDX推進〜【第1回】
2025年、後期高齢者の人口が急増し、社会保障費の倍増、医療従事者の人材不足、患者数の減少など医療機関をめぐる問題は更に深刻化する局面を迎えようとしています。そこで、課題解決の一助となると期待されているのが病院におけるDX(Digital Transformation)です。本コラムでは、病院DXの一例として現在病院が抱える3つの課題に対する施策について以下の3部構成で紹介します。... 続きを読む

インボイス制度申請締め切り迫る!医療機関のインボイス申請について。
2023年春に向けてオンライン資格確認対応、電子処方箋導入判断など、医療機関にとっては大きな対応・判断が続くなか、次なる事項として2023年10月開始のインボイス制度登録の可否といった判断が3月末までと迫っている。当社でも申請に向けて情報収集をしている状況であるが、医療機関は少し特殊な業態なため申請の判断に迷われている医療機関も多くあると思われる。... 続きを読む

2023年1月電子処方箋の運用開始。このコラムが掲載される頃は、大きな問題がなければすでに運用開始となっているだろう。電子処方箋のメリットに期待している、もしくは国の施策に賛同、今後の医療DXを意識している医療機関はすでに準備申請も済ませ、運用開始されていると思われる。今回は電子処方箋の運用に迷っている、もしくはこれから申請を検討している医療機関に向けてコラムを書かせていただきたい。... 続きを読む

いよいよオンライン資格確認義務化。病院にとって必要か。(Part2)
2021年3月25日、いよいよオンライン資格確認が開始となる予定時期であったが、先行運用で問題が発生し本格稼働が遅れるとの報道が出たことを覚えているであろうか。... 続きを読む
2021年3月下旬、いよいよオンライン資格確認が運用開始となるところであったが、先行運用で問題が多発し延期となったという報道(3月25日)があった。これらのトラブルの対応で本格稼働は10月頃の見込みとなった。... 続きを読む

前回は、改定の概要、評価の視点及び要素(第1領域、第2領域)について、変更点を中心に記述した。今回は、評価の視点、要素(第3領域、第4領域)及び訪問審査当時の進行表から見える強化項目と準備について記述したい。... 続きを読む
1997年から始まった病院機能評価における訪問審査も今年で25年が経過し、来年度からは、新バージョンの審査が開始となる。... 続きを読む


今回は、引き続き医療機関へのヒアリングから、「2022年診療報酬改定」に関わる各医療機関の具体的な算定への取り組みとその中からキーワードとして、医療機関連携と人材育成を取り上げて記述していきたい。... 続きを読む
「2022年度診療報酬改定」から1カ月たった2022年5月、事前準備や対応方法等について、いくつかの医療機関にヒアリングを行った結果、医療機関としての立ち位置や在り方等を真剣に考え、速やかな対応と将来設計に取り組んでいかなければ、今後ますます厳しい状況に立たされることが見えてきた。... 続きを読む

「PC上のその作業、ソフトウェアロボットに任せてみませんか?」(第3回)
前回のRPAの戦略的活用で医療現場の働き方が変わる!(第2回)では、3つの利用シーンを紹介した。最後となる本コラムでは、さらに3つの利用シーンをご紹介する。... 続きを読む
「PC上のその作業、ソフトウェアロボットに任せてみませんか?」(第2回)
前回は、「RPAの戦略的活用で医療現場の働き方が変わる!」の第1回として、成功事例で見る医療現場におけるRPAの活用についてのヒントと、現場で使えるRPAツール、NEC Software Robot Solution(以下RoboSol)の特徴について説明してきた。今回と次のコラムでは、前回でご紹介した事例とは異なる6つの利用シーンを紹介していく。... 続きを読む
「PC上のその作業、ソフトウェアロボットに任せてみませんか?」(第1回)
近年、時間外労働や長時間勤務が常態化している医師・看護師をはじめとした医療従事者の働き方に関して改善が叫ばれている。人材不足に加え新型コロナウイルス感染症の影響がこの状況に拍車をかける今、事務職員を含めた医療現場全体の働き方改革は急務といえる問題ではないだろうか。... 続きを読む

前回は、「2022年診療報酬改定に関わる予測について」の前編として、診療報酬改定の基本方針(骨子案)から「1.改定に当たっての基本認識」について記述した。今回は、「2.改定の基本的視点と具体的方向性」及び「3.将来を見据えた課題」について記述する。... 続きを読む
新型コロナウイルス感染症への迅速な対応が求められている中、厚生労働省は、社会保障審議会・医療保険部会で、2022年度診療報酬改定の基本方針の骨子案を示した。... 続きを読む

前回は、院内待合エリアにおける外来患者の導線に関する現状調査と、各種分析結果に基づく課題抽出等について紹介した。今回は、これらの分析結果を基にした課題の整理と改善策(提言)等について記述したい。... 続きを読む
幾度の緊急事態宣言がなされてきた中、医療機関においても更なる感染症対策が求められてきている。このような状況下において、今回は、外来患者が利用する院内待合エリアにおける感染症対策を見据えた患者導線について、1,000床規模の病院で当社が行った調査・分析事案を記述したい。... 続きを読む


新型コロナウイルス感染症の影響で病院の医業収益が減少しているが、今回は医学管理料の算定改善に効果があると考えられる「指導管理算定フォローシステム(以下、算定フォローシステム)」についてお話をさせていただく。... 続きを読む
電子カルテの普及が進み、平成29年(2017年)の厚生労働省データ(資料1)によれば一般病院で46.7%となっている。病床規模別に見ると400床以上では85.4%、200~399床では64.9%、200床未満では37.0%となっている。2021年となった今、多くの病院で更新の検討を始める時期にきているものと考える。... 続きを読む

前回はDXの概要についてお話しさせていただいた。しかしこれだけではDX推進に向けて実際なにをしていけば良いのか?と思う方も少なくないと思う。... 続きを読む
最近、医療業界でもデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)というワードを耳にすることが多くなったと感じる。医療業界のシステムベンダーや機器ベンダーなどからも、DXに対する取り組みについて話を聞く機会も増えているのではないかと考える。... 続きを読む

2020年1月、新型コロナウイルス感染症が日本で確認されて現在に至るまで、未だに収束が見えない状況である。また、これまでに2回の緊急事態宣言が発出されるなど、経済へのダメージは大きい。病院経営に関しても極めて大きなダメージを与えている。... 続きを読む

前々回からオンライン資格確認について記述してきたが、最終回の今回は、そのメリットと課題そして今後について記述する。... 続きを読む
前回は、オンライン資格確認に関する未来投資戦略と被保険者番号の導入について記述した。今回は、オンライン資格確認とそれに付随する事項について記述したい。... 続きを読む
閣議決定された「未来投資戦略2017」から4年、2021年3月末から、オンライン資格確認が始まる。今回からは、オンライン資格確認の意義について記述したい。... 続きを読む

医療・健診機関における新型コロナウイルス感染症の影響(後編:健診機関)
新型コロナウイルス感染症の影響により、今、多くの医療・健診機関で経営が悪化している。 職員の疲弊感も蔓延しており、働き方改革をはじめとした新たな取り組みが必要となってきている。... 続きを読む
医療・健診機関における新型コロナウイルス感染症の影響(前編:医療機関)
新型コロナウイルス感染症の影響により、今、多くの医療・健診機関で経営が悪化している。 職員の疲弊感も蔓延しており、働き方改革をはじめとした新たな取り組みが必要となってきている。... 続きを読む

現在、多くの医療機関においては、術式ごとに器械や物品などを正しく準備するためのチェックシートを用意しており、それに沿って器機や付帯資材等の準備を行っていることと思われるが、この準備作業は看護師の手間がかかり、準備時間の負担にもつながっている。... 続きを読む
近年、医療機関におけるICT化は目覚ましいものがあり、電子カルテの普及をはじめ、部門システムの充実といったところに注目が集まっている。このような中、今回からは院内ICTを活用したツールの事例について記述したい。... 続きを読む

今回は、前回紹介した病院経営に影響を与える医学管理料における算定フォローシステムの概要と、システム導入前に実施したシミュレーション結果に引き続き、実際に算定フォローシステムを導入した医療機関の事例について記述したい。... 続きを読む
今回より、病院経営に影響を与える医学管理料における算定フォローシステムの概要と、システム導入前に実施したシミュレーション結果について記述したい。... 続きを読む

今回も、医療セミナーにて株式会社クロイツ代表取締役の木下 諒(きのした りょう)氏が講演された【院内の情報セキュリティに関して】について記述したい。... 続きを読む
今回は、医療セミナーにて株式会社クロイツ代表取締役の木下 諒(きのした りょう)氏が講演された【院内の情報セキュリティに関して】について記述したい。... 続きを読む

今回は2020年1月に開催された「医療セミナー2020」の中で、医療経営コンサルタントの株式会社アイ・ピー・エム 代表取締役 田中幸三氏による「医学管理料における算定フォローシステムの在り方について ~算定フォローシステムを使った医療機関への効果について考える~」についてお伝えしたいと思う。... 続きを読む

注目の「働き方改革」を考える ~2025年その先の2040年を見据えたチーム医療とICT利活用のポイント~(第2回)
今回は第2回目として「働き方改革推進・ICTの利活用」におけるポイントとして、どんなことから働き方改革に取り組むのか、今後に向けたICT利活用のためのシステム構築のポイントなどを考えてみたいと思う。... 続きを読む
注目の「働き方改革」を考える ~2025年その先の2040年を見据え中小病院がおこなう医療提供体制構築とは~(第1回)
2020年度診療報酬改定の概要が見えてきた。診療報酬全体としてはマイナス改定、本体部分は0.55%引き上げ(働き方改革推進分0.08%含む)と前回同様レベルでプラス改定、薬価は1%程度引き下げる方向で最終調整に入ったとのこと(2019年12月時点)。... 続きを読む

前回紹介した自律走行型デリバリーロボットについて、本稿では医療現場における活用方法・メリットと、それによる経営効果を説明する。... 続きを読む
日本全体で労働人口不足が年々深刻化している。また2019年4月1日から働き方改革関連法案の一部が施行されたことにより、今まで以上に「働き方」について見つめなおす必要がでてきた。限られた人員で業務を行うためには、業務内容や労働時間の見直しだけではなく、機械化や自動化を図り、リソースを最大限に活かすための施策を講じなくてはならない。... 続きを読む

医療機関における情報セキュリティの重要性について(2)
~医療機関での感染事例とセキュリティ対策状況~
今回も、前回に引き続き、社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院で院内の情報管理をされている田中龍也氏が講演された【医療機関における情報セキュリティの重要性について】から、「コンピューターウイルスの脅威とは」と「事例紹介」、「医療機関のセキュリティ対策状況は」、「まとめ」について記述したい。... 続きを読む
医療機関における情報セキュリティの重要性について(1)
~安全で安心の医療を行うためのリスク対策~
今回は、社会医療法人祐生会みどりヶ丘病院にて実際に院内の情報管理をされている田中龍也氏が講演された【医療機関における情報セキュリティの重要性について】から、「情報セキュリティを気にしなければならない」と「情報セキュリティの脅威とは」について記述したい。... 続きを読む

入退院支援加算に着目した病院構造改革(4)
~2025年問題、その先の2040年問題に備えた病院構造改革~
今回も、2019年1月に開催された医療セミナー2019のセミナー後記として、お話をしたい。... 続きを読む
入退院支援加算に着目した病院構造改革(3)
~患者様満足、業務効率化、経営効果につなげる入退院支援システム~
今回も、2019年1月に開催された医療セミナー2019のセミナー後記として、お話をしたい。... 続きを読む
入退院支援加算に着目した病院構造改革(2)
~診療報酬改定による入退院支援の評価とPFM理論~
今回も、2019年1月に開催された医療セミナー2019のセミナー後記として、お話をしたい。... 続きを読む
入退院支援加算に着目した病院構造改革(1)
~人口動態によって変化する医療需要総量と病院経営~
今回も、2019年1月に開催された医療セミナー2019のセミナー後記として、お話をしたい。... 続きを読む


今回は、電子カルテの導入における医学管理料の効率的算定について、医学管理料に関する診療録の記載と診療記録の質的監査について記述したい。... 続きを読む

【セミナー後記II】病院情報ソリューションの導入効果とシステム担当の役割
今回も前回に引き続き、2018年6月に開催された医療セミナー2018のセミナー後記IIとしてお話をしたい。... 続きを読む

前回のコラムにて、パワハラを受けたと感じた人のその後の行動で、「何もしなかった」と回答した割合が約4割程度であった、というお話をしたが、その理由は何であったのだろうか。... 続きを読む
一昔前は、上司が部下に対する指導という名目で表面化することは、あまりなかったが、近年は、メディアが積極的に取り上げていることもあり、クローズアップされてきた問題となっている。... 続きを読む
今回からは、最近メディアでも数多く取り上げられている「パワーハラスメント」について、お話をしたい。筆者自身も数多くの医療現場に出入りする中で、そんな場面に遭遇することもあったが、内容については、事例として後記する。... 続きを読む

平成30年度(2018年)診療報酬改定!入退院支援加算から見る医療・介護情報連携(第3回)
「入院早期から支援を行うことで退院に向けた問題の早期把握と退院後の療養へ向けて本人、家族の安心へ繋げる」ということへの評価として退院支援加算が前回改定で設定され、医療機関では退院調整という言葉を頻繁に耳にするようになりました。... 続きを読む
平成30年度(2018年)診療報酬改定!入院基本料全般について(第2回)
平成30年度診療報酬改定まで秒読みとなりました。先日とある病院の事務長様とお話をさせていただきましたが診療報酬改定の話題で持切りといった感じです。それぞれの病院でも関係する報酬体系には注目されていることと思います。... 続きを読む
平成30年度(2018年)診療報酬改定!注目の一般病棟入院基本料の再編と統合について
平成30年度診療報酬改定まで秒読みとなりました。先日とある病院の事務長様とお話をさせていただきましたが診療報酬改定の話題で持切りといった感じです。それぞれの病院でも関係する報酬体系には注目されていることと思います。... 続きを読む

厚生省からは次期診療報酬改定の方針として、更なる地域包括ケアシステム構築強化が推進される状況です。各医療機関ではその方針を考慮して在宅診療の強化等を検討する施設も多くなっていると思われます。... 続きを読む

次期病院機能評価(機能種別版Ver.2.0)についての情報提供と考察(まとめ)
前回は、第4領域(理念達成に向けた組織運営)に関する変更点について記述したが、今回は、まとめとして、機能種別版Ver.2.0における「機能種別固有の変更点」や「評価方法の強化」について記述したい。... 続きを読む
次期病院機能評価(機能種別版Ver.2.0)についての情報提供と考察(第3回)
前回は、第1領域(患者中心の医療の推進)と第2領域(良質な医療の実践1)における全ての機能種別に共通した変更点について記述したが、今回は、第4領域(理念達成に向けた組織運営)に関する変更点について記述したい。... 続きを読む
次期病院機能評価(機能種別版Ver.2.0)についての情報提供と考察(第2回)
前回は「一般病院3」についての情報提供と考察をお話ししたが、今回は、評価項目の改定についての変更点や注意点等について記述したい。... 続きを読む
次期病院機能評価(機能種別版Ver.2.0)についての情報提供と考察(第1回)
今回は、次期病院機能評価(機能種別版)のVer.2.0についての情報提供と考察と題して、お話をしたい。... 続きを読む

改正個人情報保護法の全面施行とデータ活用
~医療・介護現場での取扱い場面毎の必要な対応について~
改正個人情報保護法(以下、改正法)が今年5月30日に全面施行された。これによりルールに基づき匿名加工された情報は本人同意なしにデータ活用できるようになった。... 続きを読む

病院IT化に伴うリスクと「対応・対策」を考える3 ~医療機関における情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の活用~
今回は「医療機関における情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の活用」と題してISMSの簡単な説明とISMSの方法論を使った医療機関情報マネジメントについてお話しさせていただきます。... 続きを読む
病院IT化に伴うリスクと「対応・対策」を考える2 ~医療機関ができる効果的な情報セキュリティ対策~
IT化を実施した医療機関が情報やシステムの安定的な管理運営を行うために必要なことはシステムセキュリティ対策、職員に対する教育と運用管理規程に定めた事項の徹底だと思います。今回はそれらについてお話をさせていただきます。 ... 続きを読む
病院IT化に伴うリスクと「対応・対策」を考える ~患者情報漏洩を防ぐには~
電子カルテの普及に伴い情報共有など医療従事者にとって利便性が向上した反面、紙カルテを使用していたときには考えられない「システムダウン、情報漏洩」といったリスクがIT化の副産物として発生しました。... 続きを読む
医療機関には様々なデータが存在し、それらを2次利用することにより、病院の状況等を把握し、病院の経営に役立てていることと思います。今回はそのようなデータの中から「検査件数・患者数」のデータを使用した「放射線検査の診療科別シェア率(必要度)」といったところに着目して高額医療機器の機種選定を中心に考察します。... 続きを読む


データを読み・解く~目の前の宝物(データ)をどのように活用するか~(高知開催分III)
今回も、2016年11月に開催された医療経営戦略セミナーについてお話をしたい。前回は、他の講演の中から「看護師不足対策なんてない。みんなの幸せを目指します。」についてお話ししたが、今回は、もう一人の講師の講演から、「データを読み・解く~目の前の宝物(データ)をどのように活用するか~」について、お話しする。... 続きを読む
医療経営戦略セミナーについて ~これからの地域医療に向けた病院経営の勘所~(高知開催分II)
前回、筆者の講演内容についてお話ししたが、今回からは、他お二人の講師の講演の中から、「看護師不足対策なんてない。みんなの幸せをめざします。」、「データを読み・解く」について、お話しする。... 続きを読む
医療経営戦略セミナーについて ~これからの地域医療に向けた病院経営の勘所~(高知開催分I)
今回は、2016年11月に開催された医療経営戦略セミナーにて講演を行ったので、その内容についてお話をしたい。... 続きを読む

今回は、データの二次利用に関する事例として、室料差額データの分岐がもたらした効果(意識改善と収入アップ)について、お話をしたい。... 続きを読む
今回は、データの二次利用に関する事例として、放射線機器の使用分析や室料差額の分析がもたらした効果(収入と意識改善)等について、お話をしたい。... 続きを読む
今回からは、「医療機関における統計データの活用に関する考察」としてお話をしたい。医療機関には、様々なデータが存在する。... 続きを読む


今回も、2016年度の診療報酬改定の概要から、「医療技術の適切な評価」及び「効率化・適正化を通じて精度の持続可能性を高める視点」について、お話をしたい。... 続きを読む
今回も、2016年度の診療報酬改定の概要から、「患者にとって安心・安全で納得できる効果的・効率的で質が高い医療を実現する視点」及び「重点的な対応が求められる医療分野を充実する視点」について、お話をしたい。... 続きを読む
今回も、平成28年度の診療報酬改定の概要から、「地域包括ケアシステムの推進と医療機能の分化・強化、連携に関する視点」について、お話をしたい。... 続きを読む


[第3回] 医療等分野の情報連携に用いる識別子(ID)の体系
前回、地域包括ケアシステムにおける情報連携に関わる「地域医療連携用ID(仮称)」及びそのIDを含めた「医療等分野の識別子(ID)の体系」についてお話しました。今回は、最終回として、「医療等分野の識別子(ID)の普及に向けた取組」についてお話しします。... 続きを読む
[第3回] 医療等分野の情報連携に用いる識別子(ID)の体系>
前回、医療機関に関係が深い「医療保険のオンライン資格確認の仕組み」についてお話しました。今回は、厚労省報告書に基づいて、「医療等分野の情報連携に用いる識別子(ID)の体系」についてお話しします。... 続きを読む
前回、序論として、厚労省報告書が公表されるまでの経緯について、振り返りました。今回は、その報告書に基づいて、医療機関に関係が深い「医療保険のオンライン資格確認の仕組み」についてお話しします。... 続きを読む
厚生労働省は、「医療等分野における番号制度の活用等に関する研究会」(以下、当該研究会)の報告書(以下、当該報告書)を2015年12月10日に公表しました。議論された内容や論点を整理し、具体的な制度設計を明らかにするなど、非常に興味深い内容になっています。... 続きを読む

前回は、医療分野における番号制度の活用について、資格照会・確認を中心にお話をしたが、今回は、その利用場面についてお話をしたい。... 続きを読む
昨年の5月、政府はカルテや診療報酬明細等の医療情報に番号制度を導入する方針を正式に決定した。具体化に向けた検討は継続中であるが、マイナンバーのシステムと医療関連のシステムを連動させ、2018年度から段階導入を行い、2020年度より本格的な運用を開始する予定である。... 続きを読む

平成27年10月 -病院に関係する様々な制度の施行や変更(2)-
前回は、平成27年10月から施行及び変更が行われた様々な項目の中から医療分野に関係する内容の一つとして「医療事故調査制度」についてのお話をした。今回は、もう一つの「特定行為に係る看護師の研修制度」についてお話をしたい。... 続きを読む
平成27年10月 -病院に関係する様々な制度の施行や変更(1)-
今回は、平成27年10月というテーマでお話をしたい。皆さん既にご存知の通り、10月から様々な制度の施行や変更が行われた。... 続きを読む


今回は最終回として、第3区分の「特定個人情報の安全管理措置等」を含め、医療現場のマイナンバー実務対応のための導入プロセスについて、お話しします。... 続きを読む
前回は、特定個人情報ガイドラインに基づいて、第1区分の「特定個人情報の利用制限」について、具体的に「しなければならない」ことや「してはならない」ことなどをお話ししました。今回は、第2区分の「特定個人情報の提供制限等」について、お話しします。... 続きを読む
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて(第2回)
前回、マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要をお話ししました。 尚、マイナンバー法附則では、「法律の施行後3年を目途として、法律の施行状況を勘案し、マイナンバーの利用範囲の拡大や、情報提供ネットワークシステムを利用した特定個人情報の提供範囲の拡大について... 続きを読む
当コラムでは、マイナンバー制度開始を目前に控えて、医療機関の情報セキュリティ・マネジメントにおけるチェックポイントについて、マイナンバー実務対応に的を絞り、4回シリーズでお届けします。... 続きを読む

病院IT化 成功のカギ -電子カルテ導入プロジェクトマネジメントをしっかり考える(2)-(第4回)
今回は第4回「電子カルテ導入プロジェクトマネジメントをしっかり考える(2)」としてキックオフからシステム稼動とその後までを各フェーズに分けて筆者の考えやポイント等を書かせていただきます。... 続きを読む
病院IT化 成功のカギ -電子カルテ導入プロジェクトマネジメントをしっかり考える(1)-(第3回)
シリーズ「病院IT化 成功のカギ」今回は第3回「電子カルテ導入プロジェクトマネジメントをしっかり考える(1)」としてプロジェクトチーム設立からシステム決定に関する考え方について書かせていただきます。... 続きを読む
病院IT化 成功のカギ -予算決定時に導入後の病院経営までをしっかり考える-(第2回)
シリーズ「病院IT化 成功のカギ」今回は第2回として予算に関する考え方について書かせていただきます。... 続きを読む
病院IT化 成功のカギ -意思決定時に「なぜ?なんの為に導入するのか」をしっかり考える-(第1回)
今回は「病院IT化のいろは・・・」ということで全4回、導入が無駄なく、施設にとって意味のあるシステム導入に導くための「?」を筆者の経験を元に考えを述べさせていただきます。... 続きを読む

ICT導入 -地域包括ケアシステムでのICT導入で押さえて頂きたいプロセスについて-(第4回)
今回は、最終回として、ICT導入で押さえて頂きたいプロセスを、個人情報の適切な取扱いに関するマネジメントシステムのフレームワークで、お話しします。... 続きを読む
課題 -地域包括ケアシステムでのICT利活用の現状について-(第3回)
前回(第2回)、地域包括ケアでのICT利活用の現状について、お話ししました。今回は、地域包括ケアでのICT利活用の課題について、お話ししたいと思います。... 続きを読む
現状 -地域包括ケアシステムでのICT利活用の現状について-(第2回)
前回(第1回)、在宅医療・介護に関するICT政策動向について、お話ししました。今回は、地域包括ケアでのICT利活用の現状について、お話ししたいと思います。... 続きを読む
はじめに -在宅医療・介護に関するICT政策動向について-(第1回)
このコラムでは、地域包括ケアシステムを構築する上で必要不可欠である多拠点・多職種間の連携、協働のためのICTに焦点を当て、在宅医療・介護に関するICT政策動向、在宅の現場でのICT利活用の現状や課題、当該ICT導入で押さえて頂きたいプロセスなどについて、4回シリーズでお届けしたいと思います。... 続きを読む

今回は、医療機関におけるメンタルヘルス対策についてお話をしたい。近年、生活習慣病をはじめ様々な疾病に対する国民の関心や認識が高まる時代になっている。... 続きを読む


前回は、医療従事者と患者のギャップから生じたトラブルの要因についてお話ししたが、今回は、その事例についてのお話をしたい。... 続きを読む
前回は、日本医療機能評価機構による医療安全に関する報告事例の検証をお話ししたが、今回は、「医療安全教育研修から」という内容で、医療従事者と患者のギャップから生じたトラブルの要因と事例についてのお話をしたい。... 続きを読む
今回からは、「医療安全対策と機能評価に関する考察」と題し、医療安全対策の現状と病院機能評価における医療安全関連項目のポイントについて、お話をしたい。... 続きを読む


病院独自の接遇文化を築く ~医療者の自発的行動を引き出すために~(第4回)
3回にわたり様々な観点から医療接遇について述べてきました。最終回の今回は、医療接遇を病院文化として定着させるまでを考えていきます。... 続きを読む
医療接遇と医療安全の関係 ~挨拶から始める「安心・安全」の医療環境づくり~(第3回)
これまでは、医療接遇が患者さんや職員にもたらす影響を考えてきました。今回は医療接遇と医療安全の関係について取り上げてみます。... 続きを読む
医療者間で共有したい思いやりの心 ~質の高い医療に欠かせない医療接遇~(第2回)
前回は、患者さんが病院や職員に何を望んでいるか、その希望や期待に応える方法のひとつとして医療接遇を取り上げました。2回目の今回は、医療接遇と職員満足度の関係について考えてみます。... 続きを読む
患者さんの立場から考える医療接遇 ~患者さんが病院や医療者に望んでいることとは?~(第1回)
「おもてなし」があらゆる業種で頻繁にとりあげられる昨今ですが、その重要性は病院等の医療機関においても例外ではありません。当コラムでは、“患者さん応対=医療接遇”を通して、今後求められるより良い病院のあり方・病院経営について、4回シリーズでお届けしてまいります。... 続きを読む

地方診療圏における「看・看連携」への取り組みについて(第5回)
これまで4回にわたって、私たちが活動を行なっている福岡県・熊本県の県境を越えた「有明地区看・看連携」についてお話をさせていただきましたが、早いもので今回が最終回となりました。... 続きを読む
地方診療圏における「看・看連携」への取り組みについて(第2回)
前回は、私が勤務する福岡県大牟田市、隣接する熊本県荒尾市を中心とした有明医療圏についてお話をさせていただきました。今回は、「有明地区看・看連携」の誕生の経緯・目的についてお話をさせて頂きます。... 続きを読む
地方診療圏における「看・看連携」への取り組みについて(第1回)
2014年、私たちにとっては一番気がかりだった診療報酬改定が4月にありました。今回の診療報酬では、もちろん2025年を見据えてですが、「機能分化」「機能強化」「在宅医療の強化」「地域医療連携」などがポイントとなっています。... 続きを読む

前回は、「急性期」を中心にお話をしたが、今回は、「亜急性期・回復期」、「外来」を中心にお話をしたい。主なポイントしては、「亜急性期・回復期」に「地域包括ケア病棟」、外来に「主治医機能」の評価が創設される。... 続きを読む
今回は、診療報酬改定2014と今後の診療体制に関する考察としてお話をしたい。今回の改定は、前回の改定と同様に、「2025年モデル」へ向けての改革促進を受け継いだ内容になっている。... 続きを読む

2014年1月に病院経営セミナーを開催いたしました。本コラムでは、医療情報データの見える化を効率的に実現するために電子カルテや医事システムを利用し、臨床指標を抽出し病院経営及び職員への意識向上を図ることがいかに重要か説明しています... 続きを読む

DPC対象病院にとって、出来高で算定している「手術」の件数を増やすためにも、手術室の運用カイゼンは欠かせません。そのため、前回は、手術室の運用カイゼンが困難だった事例をもとに、トップのコミットメントの重要性を解説しました。... 続きを読む
現在、多くの急性期病院がDPC制度を導入しています。DPC制度上でも出来高算定できる手術は病院収入に占めるウエートが大きく、急性期病院として生き残るためには、... 続きを読む
第1回 病院は赤字から脱却なるか ~“名医”という理由で院長に任命されたら…~
ある公立病院(地域中核病院)で、臨床一筋、粉骨砕身患者さんのために尽くしてきた副院長が院長に抜擢されました。彼は“名医”だったからこそ臨床の手腕を買われたわけですが、... 続きを読む

第4回 診療報酬改定で新たな施設基準を取得する際に患者様へ伝えるべきポイント
診療報酬改定のタイミングに診療機能を強化する目的で、新たな施設基準の取得を検討する病院は多いと思います。... 続きを読む
第3回 患者アンケートから読み解く! 患者さんへの応対のあり方
- 患者さんは病院の医師・受付職員をこんなふうに見ている!-
弊社では患者アンケートを実施して、病院経営の改善のヒントを発見頂くサポートをしております。今回は患者アンケート結果から患者さんが医師・受付スタッフに対して抱く不満コメントや、... 続きを読む
第2回 患者様のクレーム対応のポイント
~患者様のクレームに真摯に向き合う対応こそが患者満足度向上につながる~
患者様からのクレーム対応について現場任せになっているケース、クレーム対応マニュアルは整備されているが活用されていない、病院組織として統一したクレーム対応方法が共有されていない等、... 続きを読む
第1回 多くの患者様から選ばれている病院が実践している! 患者様の立場に立った「気配り」の実践事例
本コラムは医療業界におけるトピックス的テーマを取り上げ、情報提供していきます。今、病院においては、病院の経営改善の源泉として患者様の満足度向上が大きなテーマとなっています。今回はこのテーマを取り上げます。... 続きを読む

今回からは、病院経営分析と原価計算についてお話をしたい。
最初に、病院経営改革の概要について、述べて行きたい。一般的には、経営分析や原価計算は、病院経営改革の一旦(基礎資料)として行われ、その結果を活用して、改革の道しるべとする。... 続きを読む

今回は、2013年6月に開催された「医療機関における臨床指標のあり方とデータの2次活用」のセミナー後記としてお話をしたい。... 続きを読む
先月に引き続き、臨床指標についての話を進めたい。
前回、脳卒中2病日以内の抗血栓療法の有効性というプロセス評価についてお話をしたが、続きとして、アウトカム評価における糖尿病のコントロール率について考えて行きたい。... 続きを読む
2010年から始まった日本病院会の「QIプロジェクト」。
医療の質の向上を目的に臨床指標を活用することで、医療現場の質の向上に役立てようとしている。今年5月、新たに2013年度分の指標が発表された(※療養及び精神病床についても指標が提示されているが、ここでは、一般病床の指標について考察したい)。... 続きを読む
今後の医療において、「医療の質の向上」は重要なキーワードである。そんな中、2010年、「医療の質の評価・公表等推進事業」を厚生労働省が立ち上げた。それを引き継ぐ形で、日本病院会がQIプロジェクト(QI推進事業)として再出発させ、4年目を迎えようとしている。... 続きを読む


今月は、1月23日より開催されるセミナーの概要についてお話したい。
現在、電子カルテは、大規模病院群で7割、中規模病院群で3割、小規模病院群では1割程度が採用され、医療機関全体では約2割程度となっている。... 続きを読む
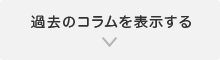

新病院機能評価について、2回目の今回は、新病院機能評価の審査方法と取り組みへの注意点についてのお話をしたい。
今回の改訂で大きく変わった点は、3点ある。... 続きを読む
今回からは、10月より受付が開始され、2013年4月より訪問審査が始まる新しい病院機能評価について、2回にわたりお話をしたい。
1995年に日本医療機能評価機構が設立され、1997年より訪問審査が始まった。それから15年、新病院機能評価として新たな評価体系が構築された。... 続きを読む

前回は、共通番号制度についてお話をしたが、今回はこの制度が及ぼす医療・福祉への影響についてお話をしたい。
2012年現在、電子カルテの普及率は全体の20%台と言われている。
EMR⇒EPR⇒EHRと進んでいく必要がある中で、まだまだ普及が進んでいない現実がある。特に、中小の病院及び診療所では、手書きのカルテが多数存在している。... 続きを読む

前回の「データ抽出のポイント」いかがでしたでしょうか?
エクセルをデータベースとして使う場合、データの形式がポイントになることをご紹介しました。
この形式でデータベースを整理すると、データ抽出のほかにデータ集計も可能になります。
また、データ抽出のポイントとして、オートフィルタを使った簡単な抽出方法をご紹介しました。... 続きを読む
さて2回目は、「データ抽出のポイント」をご紹介します。
エクセルで大量のデータから目的の値を抽出する際、どうしていますか?「オートフィルタを使っているけど、表の一部にしかフィルタが設定されない。」「データの範囲指定が途中になっている。」「簡単な抽出はできるけど、難しいのになると上手くできない。」などありませんか?... 続きを読む
いまや日常業務に欠かせないワードやエクセル、皆さん使いこなしていますか?
「パソコン教室で習ったけど、業務とどう結びつけたらいいか分からない」「もっと効率のいい方法があるはずだけど、忙しくて手作業でやっている」などありませんか?... 続きを読む

今月は、6月13日より開催されるセミナーの概要についてお話します。
今回は、2012年1月に開催された「職員育成と人事考課のあるべき姿」の詳細編として、実際の病院事例を紹介します。
この病院は、地方の求人困難な地域にありながら、独自の考え方と取り組みにより、人事体制の構築が成功しているといえる医療機関です。... 続きを読む

今回は、病院物語IIとして「病院存続のあり方(継承とM&A)」と称してお話をしたい。
近年、病院の継承問題を抱えている法人が多くなってきている。それに呼応するかのように専門のコンサルタントの台頭も目立ってきている。
中には、弁護士等が仲介、斡旋を行っているようなケースもあり、様々な形態でM&Aが行われている。... 続きを読む
今回は、病院物語として「孤独な独裁は、破綻への道」と称してお話をしたい。
どの種の企業でもそうではあるが、独裁と呼ばれる経営者は多数存在する。その企業が全て破綻しているかと言えば、「ノー」である。では、なぜ継続できているのか。... 続きを読む

前回に引き続き、診療報酬改定について、その背景と今後のお話をしたい。
今回は、在宅医療の促進について考察したい。既にご存知のこととは思うが、今後は、在宅での療養及び看取りがよりいっそう進められていく。
急性期⇒回復期⇒在宅医療、医療療養⇒在宅療養⇒在宅看取り、入院による傷病の治癒と在宅による機能の回復及び看取りが機能分化され、それぞれが果たすべき役割が明確になってくる。... 続きを読む
今回の診療報酬改定について、その背景と今後のあり方についてお話をしたい。
最初に感じたことは、いよいよ本格的に病院の機能分化が進んでいくことになったという印象である。
まずは、現在最も多い7:1体制の絞り込みが始まる。7:1の設置当初、かなり無理をして、その体制を構築した医療機関も多い。... 続きを読む

前回、教育プログラムについての話をしたが、今回は人材の評価を行う「人事考課」のあり方について述べて行きたい。
一昔前までは、人事考課を実施している医療機関は少なかったが、最近では、徐々に増えてきてはいる。
しかしながら、その人事考課が十分に生かされている医療機関が少ないもの事実である。... 続きを読む
前回、教育体制についての話をしたが、その体制構築において、全員の教育・研修ということも忘れてはならない。
研修に参加した職員のみではなく全職員が同じ情報を共有できるような仕組みを構築すべきである。最近は、グループウエア等を活用し職員全員の閲覧履歴を管理している医療機関も増えてきている。... 続きを読む
医療機関における最も大きな財産とは、なんであろうか。ある人は、「患者のリピート率である」と答えるかもしれない。
確かにリピート率が高いということはその病院を患者が頼りにしている証拠であり、病院経営上も必要なことである。しかしながら、その環境を作っているのは、病院の職員であり、質の高い職員が多い病院は、自然とこのリピーター率も上がっている。... 続きを読む

第7回 医療情報システムの情報セキュリティ確保に関しての総括 
これまで、厚生労働省の発行した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.1版(以降、今回のコラムでは『厚労省ガイドライン』と記載します。)」と、今までの経験してきた医療機関での情報セキュリティ構築支援活動を踏まえて、医療機関の方々が現在ご利用(あるいは今後ご利用予定)の医療情報システムに対して、どのようなご利用・ご運用が望ましい姿であるのかを考察して参りました。... 続きを読む
今回は、「外部保管」ついて考察して参りますが、参照すべきガイドラインとして、企業のデータセンター等を活用する場合、さらに3つの勘案すべきガイドラインがあります。... 続きを読む
今回は、前回に引き続き、「保存性」に関しての補足として、「(4)媒体・機器・ソフトウェアの整合性不備による復元不能の防止」と「機器・ソフトウェアの品質管理」」について考察して参ります。... 続きを読む
今回は、ガイドラインの「7 電子保存の要求事項」における対応に主眼をおいて考察して参ります。
今回は、「保存性」への対応について考察して参ります。... 続きを読む
本コラム第1回でご案内致しました通り、ガイドラインには『最低限のガイドライン』をそれぞれの項目に設けていますので、最低限のガイドラインを如何に実践していくべきかを順次考察して参ります。
今回は、「見読性」への対応について考察して参ります。... 続きを読む
今回は、ガイドラインの「7 電子保存の要求事項」における対応に主眼をおいて考察して参ります。
「電子保存の要求事項」に『真正性・見読性・保存性』という3つのキーワードがあり、ガイドラインの運用上の根幹と言って過言ではないと考えます。... 続きを読む
今回から連載致します「医療情報システムにおいて、情報セキュリティの定着させるためには」は、平成22年2月、厚生労働省が発行した「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.1版(以降、『ガイドライン』と記載します。)」を機軸に、今まで当方が経験してきました医療機関における情報セキュリティ構築支援活動を踏まえて、医療機関の方々が現在ご利用(あるいは今後ご利用予定)の医療情報システムに対して、どのようなご利用・ご運用が望ましい姿であるのかを考察してみました。... 続きを読む

医療情報の管理には、細心の注意を払うことが必要である。安定稼動の確保は必須であり、システムが止まると診療も止まるは、あってはならないことである。
しかし、以前は行われていたシステムが止まったときの紙による運用シミュレーションは行われなくなってきている。障害対策という意味合いでも、年に1度はシステム障害対策訓練を行うべきである。... 続きを読む
近年、医療情報システムの進歩は目覚しく、今や情報システムがなくては病院経営が出来ない状況になっている。
しかしながら、医療情報システムは導入しているが、うまく活用できていない医療機関が多いのも事実である。... 続きを読む

今回は、「医療統計」のポイントについてお話をしたい。
まず、「医事統計」のポイントであるが、この分野は、ほとんどの医療機関で整備されており、特にお話をすることは無い。
だが、一つだけ、「平均在院日数」の計算式について、お話をしたい。... 続きを読む
先日、医療統計についての講演を行ったが、今回はその概要についてお話をしたい。
医療統計といっても幅広く、それらをタイプ別に分けることから始めている。
その4つとは、「医事統計」、「医療統計」「臨床統計」「経営統計」である。... 続きを読む